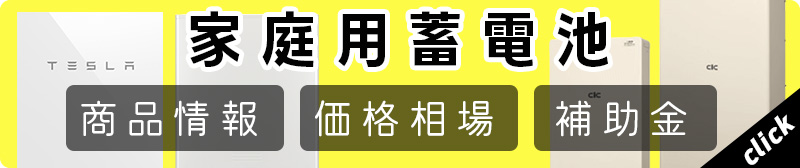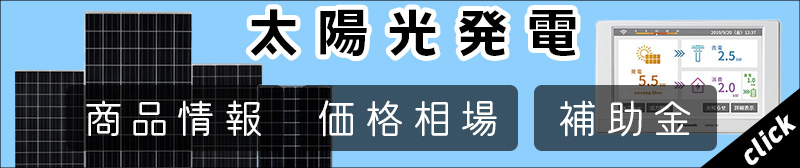蓄電池はバッテリーに電気を貯められる充電装置です。地球温暖化対策や電気料金の節約などへの効果が期待されるほか、新たな住宅設備としても注目を集めています。
わが家にも蓄電池を導入したいけど、実は仕組みや特徴をよく知らない…という人も多いかもしれません。
この記事では、蓄電池の基本的な仕組みからメリット・デメリットまでを解説しています。蓄電池の全体像をご理解いただく機会になれば幸いです。
家庭用蓄電池の価格と商品比較
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
蓄電池とはどのようなものか

蓄電池とはどのようなものか、基本的な仕組みからチェックポイント、注意点までを解説します。
蓄電池とは
蓄電池とは、文字通り電気を蓄えられる充電装置のことです。充電と放電を繰り返しながら、継続的に電気を使用しつづけられます。
電池には2種類あります。なじみのある乾電池のように、一度使い切ったら再度充電して使用することができないものは「一次電池」です。一方、一度使い切っても再び充電して繰り返し使用できるものは「二次電池」と呼ばれます。
蓄電池はこの二次電池に含まれており、使い切っても再び充電が可能です。充電して繰り返し使える二次電池は環境にやさしく、コスト削減をしやすいといったメリットがあります。
蓄電池の基本的な仕組み
蓄電池は化学反応を用いて電気を作り出し内部に蓄えています。内部は+(プラス)極と-(マイナス)極の金属と電解液によって構成されており、電極に使用する素材によっていくつか種類がありますが、基本原理はどれも同じです。
プラス極とマイナス極の間を電子が動くことで電流が生じ、充電したり放電したりすることができます。それぞれの金属(電極)の特徴は、プラス極がイオン(+)に溶けにくい金属、マイナス極がイオン(+)に溶けやすい金属です。この性質の違いを利用して、電子がマイナスからプラスへ動くことによって電流が生じる仕組みです。
電気は「電気のまま」貯めることができない
蓄電池が注目を集めている根本的な理由は、電気は電気エネルギーのまま貯めることができないからです。例えば、昼間に太陽光発電設備で作った電気は、そのままの状態で夜まで蓄えることはできません。
蓄電池は化学反応を用いて電子を動かし、電気エネルギーから化学エネルギーに変換して貯める仕組みです。エネルギーの形を変えて、エネルギーの蓄積ができるようになります。
なお、電気エネルギーを位置エネルギーに変換して蓄積するのが、揚水発電です。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
蓄電池の種類
蓄電池にはいくつかの種類がありますが、代表的なのが「リチウムイオン電池」「ニッケル水素電池」「鉛蓄電池」「NAS電池」です。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、用途やコストに応じて選ばれています。
リチウムイオン電池
リチウムイオン電池は、2021年時点で市場の主流となっている蓄電池で、私たちの身近なところではパソコンやスマートフォンのバッテリーとしてよく知られています。電解液に有機電解液を、プラス極にリチウム含有金属酸化物を、マイナス極に炭素材料を使用する構造を持ち、高性能で多用途に使われています。
リチウムイオン電池のメリット
リチウムイオン電池の大きな特徴は「高容量」と「高効率」です。動作電圧が高いため小型化・軽量化しやすく、省スペースで大きなエネルギーを蓄えることができます。さらに、急速充電に対応できることや、自己放電が少なく使用停止時のエネルギー消耗が少ない点も強みです。加えて、寿命は約6〜10年、充放電サイクルは3,500回前後と耐久性にも優れています。
リチウムイオン電池のデメリット
一方で、リチウムイオン電池には「コスト」と「安全性」の課題があります。レアメタルなど希少素材を使用するため、1kWあたり約20万円と導入コストは比較的高額です。また、温度変化に弱く、高温環境では発火リスクが高まる点にも注意が必要です。
リチウムイオン電池の主な用途
リチウムイオン電池は、その高性能さから幅広く活用されています。スマートフォンやパソコンといったモバイル機器をはじめ、家庭用蓄電池や電気自動車(EV)の駆動バッテリーなど、多くの先端分野を支える中心的な存在となっています。
ニッケル水素電池
ニッケル水素電池は、環境にやさしくリサイクル性が高い二次電池の一種です。電解液には水酸化カリウム、プラス極にはオキシ水酸化ニッケル、マイナス極には水素吸蔵合金を用いた構造を持っています。もともとは人工衛星用バッテリーとして開発された背景を持ち、安全性が高い点が大きな特長です。
ニッケル水素電池のメリット
ニッケル水素電池の強みは、安全性と性能のバランスにあります。急速充電に対応し、高出力放電も可能であるため、パワーが必要な用途にも利用できます。また、過充電や過放電に比較的強く、繰り返し使用できる回数が多いことから持続性にも優れています。さらに、リサイクル性が高く、環境に配慮された電池として評価されています。
ニッケル水素電池のデメリット
一方で、デメリットも存在します。自己放電が多く、使用していなくても自然にエネルギーが減ってしまう傾向があります。また、コストが高めであること、重量が重いこと、寿命が5~7年程度とリチウムイオン電池に比べて短いことが課題です。
ニッケル水素電池の主な用途
ニッケル水素電池は、幅広い分野で活用されています。時計や懐中電灯、リモコンといった身近な機器から、ハイブリッドカーの駆動用バッテリー、鉄道やモノレールといった輸送機器に至るまで、多様な用途で利用されています。特にハイブリッド車では、信頼性の高さから現在も多く採用されています。
鉛蓄電池
鉛蓄電池は1859年に発明された、最も古くから利用されている蓄電池です。希硫酸を電解液とし、プラス極に二酸化鉛、マイナス極に鉛を用いたシンプルな構造を持ちます。長い歴史の中で実績を積み重ね、現在も幅広い分野で使用され続けている信頼性の高い蓄電池です。
鉛蓄電池の大きな特徴は、その長寿命です。およそ17年という耐用年数を持ち、理論上のサイクル回数は約3,000回とされています。ただし、充電と放電を繰り返すことで効率が低下しやすいため、長期運用には注意が必要です。重量が重い点も欠点の一つです。
鉛蓄電池のメリット
鉛蓄電池の最大の強みは、コストパフォーマンスに優れていることです。他の蓄電池に比べるとエネルギー効率は低いものの、比較的安価で入手しやすく、信頼性の高い電源として長期間利用できます。そのため、古くから多様な分野で普及しています。
鉛蓄電池のデメリット
一方で、重量があるため取り扱いが難しく、繰り返し充放電するうちに性能が劣化しやすいという課題があります。また、エネルギー効率が低く、最新のリチウムイオン電池などと比べると小型・軽量化には不向きです。
鉛蓄電池の主な用途
鉛蓄電池は、自動車のエンジン始動用バッテリーをはじめ、フォークリフト、小型飛行機、電子楽器など、多様な分野で利用されています。安価で実績が豊富なことから、今なお世界中で広く使われています。
NAS電池
NAS電池(ナトリウム硫黄電池)は、日本ガイシが開発した大型蓄電池で、ナトリウムと硫黄を用いた特殊な仕組みを持ちます。大規模なエネルギー貯蔵を目的に設計されており、世界的にも注目される次世代の蓄電池の一つです。
NAS電池は高いエネルギー効率を誇り、1kWあたり約4万円という低コストを実現しています。また、長寿命で、大規模施設や電力貯蔵システムにおいて優れたコストパフォーマンスを発揮します。鉛蓄電池と比べると、約3倍の高エネルギー密度を持ち、同じ体積でもより多くのエネルギーを蓄えることが可能です。
NAS電池のメリット
NAS電池はコンパクトな設計ながら、大容量のエネルギーを蓄えられるため、再生可能エネルギーの貯蔵や電力需給の調整といった分野で高い効果を発揮します。特に、安定供給が求められる産業用途においては、その効率性とコストパフォーマンスの良さが大きな強みです。
NAS電池のデメリット
一方で、NAS電池は300℃を超える高温で作動するため、安全性の確保が不可欠です。さらに、ナトリウムや硫黄といった危険物を使用しているため、設置や保守には専門知識を持つ人材が必要になります。こうした点から、一般家庭用には不向きであり、主に大規模設備向けに活用されています。
NAS電池の活用分野と位置づけ
用途としては、工場の非常用電源や大規模電力貯蔵施設が中心です。他の蓄電池と比べると、NAS電池は「大規模運用に特化した蓄電池」としての位置づけが明確であり、今後も再生可能エネルギーの普及において重要な役割を担っていくことが期待されます。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
蓄電池のメリット

蓄電池と太陽光発電の組み合わせが生むメリット
蓄電池は太陽光発電と組み合わせて導入することで、単体設置では得られない大きなメリットを発揮します。その代表例が「余剰電力の有効活用」です。蓄電池がない場合、太陽光で発電した電気はその場で使うか、余った分を売電するしかありません。しかし蓄電池を導入すれば、昼間に発電した電気を夜間に利用できるため、家庭の電力自給率を高められます。
経済性と環境性の両立
卒FITにより売電単価が下がっても、自宅で発電した電気を蓄電池に貯めて使えば、電力会社から購入するよりも経済的にお得になるケースがあります。さらに、再生可能エネルギーを自家消費することは温室効果ガス削減にもつながり、環境貢献という観点でも大きな意義を持ちます。
ライフスタイルに応じた柔軟な運用
蓄電池を導入すると、太陽光発電の運用方法に幅が生まれます。例えば、日中の在宅時間が長く電気使用量が多い家庭では、夜間の安価な電気料金プランを活用して深夜に充電し、昼間に使用することで売電量を増やせます。これは太陽光発電の容量が比較的小さい家庭にとって効果的な方法です。
一方で、日中に電気使用量が少ない家庭では、太陽光発電で余った電気を売電し、夜間や発電できない時間帯は蓄電池に貯めた電力を活用する方が効率的です。このように、家庭のライフスタイルや電力使用パターンに合わせて運用方法を最適化できるのも、蓄電池を導入する大きな魅力です。
夜間電力の活用で電気料金を節約
蓄電池を導入する最大のメリットの一つが、電気料金の安い夜間に電力を蓄え、昼間に利用できる点です。昼間は電気代が高いため、夜間に充電した電気を日中に使うことで、光熱費を効率的に抑えることができます。
基本料金の削減につながるスマートメーター
スマートメーターが設置されていれば、電力の使用状況がデータ化され、翌年以降の契約電力や基本料金に反映されます。蓄電池を活用してピーク時の電力消費を抑えることで、基本料金を下げる効果も期待できます。スマートメーターは「電力の見える化」を実現するだけでなく、通信機能を備えているため電力会社とのデータ共有にも役立ちます。
電力会社の料金プランとAIによる自動制御
電力会社によっては、深夜帯の電気料金が安く設定されているプランが用意されています。このプランを利用すれば、深夜に安価な電力で蓄電し、昼間の電気代を抑えることが可能です。さらに近年では、AIを搭載した蓄電池も登場しています。AIが電気料金の安い時間帯を自動で判断し、最適なタイミングで充電を開始してくれるため、利用者は細かい操作をする必要がありません。
注意すべきポイント
ただし、すべての電力会社が深夜の電気代を安くするプランを用意しているわけではありません。蓄電池の導入を検討する際には、自分が加入している契約プランを確認し、必要であれば深夜料金が割安となるプランへ切り替える手続きを検討することが大切です。
蓄電池がもたらす「ピークシフト」効果
蓄電池を上手に活用することで、社会全体の電力需要のピークを抑えることができます。この仕組みは「ピークシフト」と呼ばれており、重要な役割を担っています。
電力需要が集中する時間帯
日本の電力使用量は、一般的に13時から16時の間にピークを迎えるとされています。この時間帯は多くの家庭や企業が電力を使うため、電力会社は需要に合わせて発電所をフル稼働させなければなりません。しかし、電気は石油やガスのように大量に貯蔵できないため、その時々の需要に合わせて発電量を調整する必要があります。
発電効率と蓄電池の役割
発電所は稼働や停止を繰り返すとエネルギー効率が低下するため、需要に合わせて細かく調整するのは望ましくありません。そこで、蓄電池の出番です。夜間や電力需要が少ない時間帯に充電した電気を、ピークタイムに活用することで、電力供給の山と谷を平準化することができます。
社会的・環境的な意義
ピークシフトによって発電所の効率が上がれば、エネルギー資源の無駄遣いを減らせるだけでなく、二酸化炭素排出量の削減にもつながります。これは家計に直接的なメリットをもたらすものではありませんが、日本のエネルギー事情や環境問題の解決に長期的な視点で貢献する取り組みといえるでしょう。
停電時に頼れる蓄電池の存在
自宅に蓄電池を設置しておくと、台風や地震などで停電が発生しても家庭内で電気を使い続けることができます。特に太陽光発電と組み合わせれば、昼間は発電した電気を利用できるだけでなく、夜間や雨天時など太陽光パネルが発電できない時間帯にも、蓄電池に蓄えた電気を活用できます。太陽光発電のみの場合、自立運転モードで昼間は使用できますが、日照がない時間には利用できないため、蓄電池の有無は大きな差となります。
災害大国・日本における備え
日本は地震や台風など自然災害のリスクが高く、大規模災害時には電力を含むライフラインが途絶することも珍しくありません。2011年の東日本大震災以降、家庭での災害対策として蓄電池を導入する動きが増えてきました。太陽光発電と組み合わせた蓄電池は、非常時に家庭用の予備電源として機能し、復旧までの生活を支える大きな役割を果たします。
特定負荷型と全負荷型の違い
災害時にどのように電力を供給するかは、蓄電池のタイプによって異なります。特定負荷型蓄電池は、あらかじめ設定した限られた回路(冷蔵庫や照明など)にだけ電気を供給する仕組みで、コストを抑えながら最低限の生活を維持できます。一方、全負荷型蓄電池は家中の電化製品に電気を送れるため、普段と変わらない快適な生活が可能です。ただし、その分大容量の蓄電池が必要となり、設備コストは高くなる傾向があります。家庭のニーズに合わせて、どちらを選ぶか検討することが大切です。
EV補助金と普及の後押し
電気自動車(EV)は、経済産業省が主導する補助金制度によって導入のハードルが下がり、環境意識の高い層を中心に普及が進んでいます。補助金の存在は初期費用の負担を軽減し、より多くの家庭がEVを選択する大きなきっかけとなっています。
蓄電池とEVの相性の良さ
蓄電池はEVとの相性が良いことでも知られています。家庭に蓄電池を設置すれば、太陽光発電で作った電気を一度蓄電池にため、そこからEVに充電するという流れが可能です。この仕組みによって、家庭での電力利用と車のエネルギー供給を効率的に連携させることができます。
「トライブリッド」システムの可能性
特に注目されているのが「トライブリッド」と呼ばれる仕組みです。これは、太陽光発電・蓄電池・電気自動車を一体的に組み合わせたスタイルで、電気自動車が走るためのエネルギーの大部分を太陽光でまかなえるように設計されています。
100%エコな暮らしへ
太陽光発電で生み出した電気を蓄電池に蓄え、それを電気自動車に供給する。この流れを活用すれば、ガソリンや商用電力に頼らない、文字通り“100%エコ”なソーラーカーとして走行することが可能です。再生可能エネルギーを家庭と車の両方に活用することで、環境負荷を減らしながら持続可能なライフスタイルを実現できます。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
蓄電池のデメリット

蓄電池にはメリットだけでなく、以下のようなデメリットがあります。
初期費用がかかる
家庭用蓄電池を導入する際に最も大きなハードルとなるのは、やはり初期費用の高さです。本体価格に加えて、周辺機器の費用や設置工事費用などを合わせると、総額は数十万円から数百万円に達します。そのため、電気代の削減効果や売電収入とのバランスを事前にシミュレーションし、長期的に投資を回収できるかどうかを見極めることが重要です。
補助金の活用で負担を軽減
初期費用を抑える方法の一つとして、国や自治体が用意している補助金制度を活用する方法があります。補助金の内容は地域や年度によって異なるため、自分の住むエリアで利用可能な制度を事前に確認しておくと導入コストを抑えやすくなります。
一般的な価格帯と回収期間
製品や容量によって異なりますが、家庭用蓄電池(4~8kWh程度)のシステム一式を導入する場合、相場は150〜250万円ほどです。家庭の人数やライフスタイルによって最適な容量や活用方法が変わるため、初期費用を回収するまでにかかる期間も家庭ごとに異なります。
ハイブリッド型と単機能型の違い
家庭用蓄電池には、大きく分けて「ハイブリッド型」と「単機能型」の2種類があります。ハイブリッド型は太陽光発電と組み合わせて効率的に活用できる多機能タイプですが、その分コストは高くなりがちです。一方、単機能型は太陽光と連携しない独立運用タイプで、比較的価格を抑えられるのが特徴です。
設置スペースが必要
家庭用蓄電池には屋内用と屋外用がありますが、どちらにしても設置スペースの確保が必要です。大きさはエアコンの室外機1〜2台分ほどが目安。屋外であれば大きな問題はありませんが、屋内に設置する場合は事前に十分なスペースを確認しておくことが重要です。
屋外設置での注意点
屋外型蓄電池を設置する場合には、設置環境に配慮する必要があります。直射日光が当たり続ける場所や高温多湿になる場所、結露が発生しやすい場所は避けるのが基本です。これらの条件を満たすことで、蓄電池の性能や寿命を保ちやすくなります。
屋内設置での注意点
屋内型蓄電池は、環境条件をクリアしやすい反面、運転音が気になる可能性があります。そのため、寝室や書斎、勉強部屋などの静かな環境には向いていません。設置する際には、日常生活に支障が出ない場所を選ぶのが望ましいでしょう。
環境と機器配置を踏まえた最適設置
分電盤や関連機器との位置関係によっても、屋内型・屋外型のどちらが適しているかは変わります。メーカーや施工業者に相談して、最適なタイプと設置場所を選ぶことが大切です。また、蓄電池の寿命は設置環境に大きく左右されるため、できるだけ良好な環境に設置することで長く安心して使うことができます。
蓄電池には寿命がある
蓄電池は一度設置すればずっと使えるわけではなく、必ず寿命があります。その寿命を判断する際に目安となるのが「サイクル回数」です。サイクル回数とは、満充電から完全放電までを1回として数える方法で、「0%→100%→0%」を1サイクルとカウントします。この回数には限りがあるため、蓄電池は部品が正常でも無限に使い続けることはできません。
サイクル回数と寿命の関係
サイクル回数は蓄電池の種類やモデルによって異なりますが、設置環境や使い方によっても大きく変わります。たとえば高温多湿の環境や過放電を繰り返すような使い方をすると寿命が短くなる傾向があります。
保証期間とメーカー対応
蓄電池本体の保証は一般的に10〜15年に設定されています。これは蓄電池の寿命を前提にした期間で、時間の経過とともに充電できる最大容量が徐々に低下するためです。多くのメーカーでは、保証期間内に容量が一定以下まで低下した場合に、交換や修理対応を行う仕組みを設けています。ただし保証内容や具体的な条件はメーカーごとに異なるため、導入前に必ず確認しておくことが重要です。
蓄電容量が有限である
蓄電池は平時にも非常時にも頼れる存在ですが、無限に充放電できるわけではなく、貯められる電気の量には限りがあります。容量が大きい蓄電池ほど長時間の使用が可能ですが、その分価格も高額になります。導入の際は、家庭での電気の使い方や使用時間帯、そして予算を踏まえたうえで、自宅に最適な容量を選ぶことが重要です。
容量と使える時間の関係
蓄電池の容量は「どのくらいの電気を、どれだけの時間使えるか」の目安です。たとえば、消費電力の大きな家電を長時間使いたい場合には大容量タイプが必要になります。非常時に備えて充電しておいたとしても、最大容量によって稼働できる家電の数や使用時間は変わるため、事前に想定しておくことが大切です。
普段使いでも容量管理が重要
電力会社の電気を使っていると意識しにくいですが、蓄電池を効率よく活用するには「容量を把握しながら使う」意識が欠かせません。特にリチウムイオン蓄電池は、性質上、充電した電気をすべて使い切れない仕組みになっています。容量をゼロにすると劣化が進むため、実際には残り10%前後を残して運用する必要があります。したがって導入時は、余裕を持った容量設定を考えることが望ましいでしょう。
経年劣化と交換の必要性
蓄電池は年月が経つにつれて容量が徐々に減少していきます。これは自然な劣化現象であり、寿命を迎えると交換が必要になります。導入後は定期的な点検や容量確認を行い、交換のタイミングを見極めることが長期運用のポイントです。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
蓄電池が向いているのはどんな人?
蓄電池のメリット・デメリットは把握できても、実際自分に合うのかどうか判断が付かないという人も多いでしょう。以下には蓄電池の導入が向いている人と向いていない人の特徴を列挙していきます。
蓄電池が向いている人
太陽光発電システムをすでに利用している方、あるいは導入を検討している方には、蓄電池の導入を強くおすすめします。太陽光発電と蓄電池は非常に相性が良く、組み合わせて活用することで売電量を高めたり、発電した電気を無駄なく使えるようになります。余剰電力を蓄電池にためておけば、必要な時間帯に柔軟に使えるのも大きなメリットです。
電気代削減への効果
毎月の電気代が高いと感じているご家庭にとっても、蓄電池の導入は有効です。特に深夜の電気料金が安いプランを利用すれば、電気代が安い時間帯に蓄電して、昼間の高い電気代の時間帯に使うことができます。その結果、電気代を効率的に抑えることが可能になります。
停電や災害時の備え
さらに、停電や自然災害といった非常時にも蓄電池は心強い存在です。蓄電池があれば、太陽光発電が稼働していない夜間や悪天候でも電力を確保でき、日常生活の安心感が大きく高まります。用途や目的に応じて、冷蔵庫や照明など特定の機器に電力を供給する「特定負荷型」、家全体をカバーできる「全負荷型」を選ぶと良いでしょう。
蓄電池が向いていない人
電気代があまり高くない家庭
蓄電池の導入は、毎月の電気代が高いご家庭ほど効果を発揮します。逆に電気代があまりかからない場合は、節約効果が小さいため投資回収に時間がかかり、導入メリットは薄いといえます。
日中に家を空けることが多い家庭
日中に仕事などで外出し、家庭でほとんど電気を使用しない場合も蓄電池の導入効果は限定的です。夜間に充電した電力を日中に使う機会が少なければ、コスト削減の恩恵を十分に受けにくいでしょう。
設置スペースが十分に確保できない家庭
蓄電池には一定の設置スペースが必要です。屋外や屋内に十分なスペースがない場合は、設置自体が難しくなります。また、無理に設置できたとしても、高温多湿や直射日光など不適切な環境では蓄電池の寿命が縮み、余計なメンテナンス費用や修理費用が発生する可能性もあります。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
家庭用蓄電池の価格推移

家庭用蓄電池の価格はどのように変動してきたのか、まずは近年の価格推移と今後の予測を解説します。
蓄電池の近年の価格動向と現状
家庭用蓄電池の本体価格は、技術革新や生産規模の拡大により、年々低下してきました。三菱総合研究所のデータによると、2022年度の蓄電池システム価格(工事費除く)は11.7万円/kWhで、2019年度の14.0万円/kWhから2.3万円/kWh下がりました。2015年度の22.1万円/kWhと比較すると、ほぼ半額になっています。
一方、近年は価格低下のペースが鈍化しています。背景には電子機器や電気自動車の需要増加による半導体不足、レアメタル価格の高騰などが挙げられます。また、海外からの材料費は円安の影響で上昇しています。技術革新による低価格化に対して、コストプッシュによるブレーキがかかっている状況です。
蓄電池の今後の価格動向の予測
今後、家庭用蓄電池の価格が大幅に下がる可能性は低いと考えられています。蓄電池に使用される主要な材料費が高止まりしているためです。特に製造に必要な半導体は世界的に需要が増えており、供給不足が続いています。
海外からの部材調達では円安もコスト増加の一因となっています。円高に転じればコストプッシュによる価格上昇は抑制されますが、円安が継続している現状では、蓄電池製造にかかる輸入コストへの影響は避けられません。政府や中央銀行による施策が鍵を握るものの、展望は不透明な状況です。
これらを総合すると、将来的に蓄電池価格が上昇するリスクがあると予測できます。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
蓄電池導入は早いほうがいい? 待ったほうがいい?
前述した価格動向を踏まえ、蓄電池導入は早いほうがいいのか、待ったほうがいいのか、導入タイミングを考えてみましょう。
蓄電池の今後の値下がりは期待できない
家庭用蓄電池の価格は、過去10年間で徐々に下がってきました。今後も値下がりする可能性を期待し、購入を見送ろうと考えている人も少なくないでしょう。価格がさらに下がる可能性が完全に否定されるわけではありませんが、短期的には価格が安定しており、大幅な値下がりの見込みは低い状況です。
一方、導入を遅らせることで逆にコストが増加するリスクもあります。材料費の高騰や円安傾向が続く中、コストプッシュにより価格が上昇する要因が強まっています。結果的に、比較的価格が安定している今が導入の好機と考えられます。
太陽光発電を導入している場合は蓄電が有利
固定価格買取制度(FIT)の期間が終了すると、余剰電力の売電価格は大きく下がり、以前のような収入は見込めなくなります。そのため、売電を前提にした投資効果は限定的になります。
余剰電力を自家消費に回すメリット
蓄電池を導入すれば、日中に発電して余った電気を貯めて夜間に使用できるため、電力会社からの購入電力量を減らすことが可能です。結果として、電気代の節約効果を得られ、売電よりも大きな経済的メリットにつながるケースが増えています。
卒FIT家庭にこそ有効な選択肢
特に「卒FIT」を迎えた家庭、あるいはその直前の家庭では、蓄電池の早期導入が有効です。売電収入を頼るより、自家消費にシフトしたほうが合理的であり、長期的な電気代削減やエネルギーの自立につながります。
導入判断のポイント
家庭ごとの電気使用状況によっては、FIT期間中であっても蓄電池の導入効果が十分に得られる場合があります。売電価格の今後の動向や、自宅の消費電力量を踏まえたうえで、具体的なメリットを試算することが大切です。導入に迷うときは、専門業者に相談し、自宅に合った最適な導入プランを提案してもらうのがおすすめです。
蓄電池の補助金制度が改変される可能性
蓄電池を導入する際、国や自治体が提供する補助金を利用すれば、数十万円単位で初期費用を抑えられるケースがあります。特に太陽光発電とのセット導入を条件とした補助金制度は多く、併用することで経済的負担を軽減できるのが大きなメリットです。
制度改変リスクと導入時期の見極め
ただし、補助金制度は毎年見直しが行われ、支給額が減額されたり、条件が厳格化されたりする可能性があります。中には制度自体が終了してしまう場合もあるため、補助金ありきで導入を検討している場合は、改変前に早めに購入した方が結果的に得になることもあります。
地域・タイミングごとの条件確認が必須
補助金の対象や条件は、国の制度だけでなく自治体ごとにも異なります。申込期限が設けられていたり、先着順で予算枠が埋まる場合もあるため、導入を検討する際は事前の情報収集が欠かせません。太陽光発電とのセット条件や、対象となる機種・容量など、細かい規定を確認しておきましょう。
タイミングを見極めた賢い選択を
補助金の有無は、導入コストや回収期間に直結する重要な要素です。特に「卒FIT」を控えている家庭や、電気代の上昇が気になる家庭では、補助金が活用できるうちに導入するのが合理的な選択となります。将来の制度改変リスクも踏まえて、自分の家庭にとって最適なタイミングを見極めることが大切です。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
蓄電池の設置にかかる費用の内訳

家庭用蓄電池を導入する場合、何にいくらかかるのでしょうか。本体価格と工事代を含めて設置にかかる費用の内訳を解説します。
家庭用蓄電池の本体費用
蓄電池の設置費用の中で、最も大きな割合を占めるのが本体費用です。本体費用とは、設置工事や関連機器を除いた蓄電池そのものの値段を指します。価格はメーカーや容量によって異なり、一般的な家庭用蓄電池では1kWhあたり約11.7万円が相場とされています。
1kWhとは、1,000Wの電力を1時間使用した際の電力量です。例えば、容量が5〜10kWhの蓄電池の場合、単純計算で58.5万円から117万円程度が目安となります。価格に大きな差が出る要因には、蓄電池の種類や性能、メーカー独自の技術も関係しています。蓄電池導入の総費用を算出する際は、設置費用など他の項目も加える必要があります。
家庭用蓄電池の設置工事費用
設置工事費用には、配線や基礎の施工などが含まれますが、費用は設置環境や太陽光発電システムの有無によって変わる場合があります。一般的な工事費用の目安は、三菱総合研究所の調査によれば1kWhあたり約2.2万円です。
例えば、5〜10kWhの蓄電池の場合、11〜22万円程度が相場です。ただし、蓄電池の容量そのものが工事費用を左右するわけではなく、販売や施工会社によって料金にばらつきがある点に注意が必要です。
蓄電池は新築時だけでなく、既存住宅に後付けすることも可能です。後付けの場合でも、基本的に新築時の設置費用と同等の金額がかかります。信頼できる施工会社の選定が費用を抑える鍵となります。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
蓄電池の設置費用を安く抑える方法
蓄電池の設置費用を安く抑えるためには複数の方法があります。5つの節約方法を紹介しますのでチェックしてみましょう。
太陽光発電と同時設置をする
蓄電池は太陽光発電と同時に設置すると、設置費用を抑えられるメリットがあります。セットで導入する場合、工事費用やシステムの購入価格に対して割引が適用されるケースが多いためです。太陽光発電と蓄電池を個別に設置すると、別々に工事を依頼する必要があり、結果として人件費や施工費が二重に発生します。同時設置なら工事の効率が向上し、全体の費用が軽減されます。
一部自治体では「太陽光発電と蓄電池のセット導入」を補助金申請の条件となっている場合があり、同制度を活用して、初期費用を抑えられます。また、FIT期間終了後も余剰電力の自家消費が可能となるため、電気料金の節約効果が高まります。同時設置により、初期費用と長期的なコスト削減を見込めるだけでなく、補助金の利用効率も向上しますので、導入時には検討する価値があります。
複数社から見積もりを取る
蓄電池の設置費用を抑えるためには、複数の業者から見積もりを取るのが基本です。複数社に見積もりを依頼すると、市場の価格帯やサービス内容を把握できるため、適正価格で導入が可能になります。相場が分かれば、提示された見積もりが妥当かどうかの判断も容易になります。費用面での交渉もスムーズに進められ、費用削減に繋がりやすくなります。
複数の施工会社に見積もりを依頼すると競争原理が作動しやすくなり、各社が価格や条件の面で最大限の提案をする可能性があります。結果、設置費用が抑えられるだけでなく、サービス内容が充実した施工会社を選べる可能性も高まります。価格面だけでなく、アフターサポートや保証内容も比較し、総合的に最適な施工会社を選びましょう。
国・自治体からの補助金を確認する
蓄電池の設置費用は、自己資金だけでなく、国や自治体が提供する補助金を活用する方法も有効です。補助金を利用すると、購入費用が軽減され、高額な蓄電池でも導入しやすくなります。特に、太陽光発電と蓄電池をセットで設置する場合、費用面での負担をさらに軽減できる可能性があります。
ただし、補助金の利用には注意が必要です。例えば補助金は予算がなくなり次第、申請受付が終了します。また、地方自治体による補助金制度は地域によって申請期間や条件が異なります。国と自治体の補助金は併用できる場合がありますが、自治体の補助金が国の原資を基にしている場合、併用が制限されるケースもあります。
蓄電池導入を検討する際には、国や自治体の公式サイトで補助金の最新情報を確認し、条件や申請期限をしっかり把握しましょう。施工会社に補助金申請について相談することで、手続きがスムーズに進む場合もあります。
補助金を利用する際の注意点
蓄電池の補助金制度は誰でも利用できる訳ではなく、蓄電池の種類や設置時期といった所定の条件を満たす必要があるので十分に注意しましょう。
補助金を当てにして蓄電池を導入しても、対象外だったために交付が受けられなかったとなれば大きな痛手になります。
各補助金制度で定められている条件が異なるので、導入前には入念に確認してください。また、各補助金制度は申請期間が設けられているのが一般的です。
そのため、条件を満たしていても申請期間を過ぎている場合は受け付けてもらえません。
仮に、申請期間内であったとしても、申し込みが補助金の予算に到達した際には早期終了となるケースもあります。
補助金制度は条件と申請期間を確認した上で、早めの申請を心がけましょう。
メリットとデメリットを比較して導入を検討しよう!
蓄電池は安い買い物とは言えないので、メリット・デメリットを熟慮して導入の可否を決断しましょう。
初期費用を抑えるには補助金制度も重要ですが、機種や工事内容の違いを一括見積りで比較するのも有効です。
株式会社ゼロホームが運営するサービス「エコ発電本舗」では幅広いメーカーの蓄電池を取り扱っており、工事体制やアフターサポートも万全となっています。
まずは無料見積りから費用の目処を付けてみてください。
ソーラーローンを利用する
蓄電池の導入費用を抑える手段として、ソーラーローンの利用もおすすめです。ソーラーローンは、都市銀行や地方銀行、信用金庫、信販会社などが提供する融資サービスで、太陽光発電や蓄電池の設置に特化しています。金融機関によってローンの条件やサービス内容は異なり、個別のニーズに合わせた選択が可能です。
ソーラーローンは一般的に低金利で融資が行われるため、利息負担を抑えやすいのがメリットです。売電収入と電気代節約部分を充当しての返済が可能となります。初期費用の高額さが導入の障壁となる場合でも、資金調達の選択肢として有効です。
蓄電池の設置はお早めに検討を!
蓄電池の価格は年々下がってきましたが、材料費の高騰や円安などの影響を受け、価格低下が鈍化しています。今後蓄電池が大幅に値下がりすることは期待しづらく、現在の価格が比較的安定している時期と言えます。蓄電池の設置を検討している方にとっては、早めに決断するのが賢明です。
予算だけでなく、ニーズに応じた適切な容量を持つ蓄電池を選ぶことが大切です。知識と経験豊富な専門会社に相談すれば、よりスムーズに導入が進むでしょう。エコ発電本舗では、無料見積りや無料相談を提供していますので、ぜひご利用ください。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
蓄電池のメーカーごとの選び方
家庭用蓄電池を選ぶときのチェックポイント
蓄電池のメーカーを選ぶ前に、チェックしておきたいポイントが幾つかあります。
良いメーカーの製品を選んでも、自身のニーズに合っていないと後悔しかねません。
そこで、自身のライフスタイルなどにあわせた、蓄電池選びのポイントを紹介していきます。
蓄電池の蓄電容量
蓄電容量とは、バッテリーに貯められる電気の量のことです。この容量が大きいほど、多くの電気を貯めて長時間使えるようになります。大きい方が有利に見えますが、必ずしもそうではありません。
使いきれないほどの量を貯められる製品を購入すると、性能を活かしきれず、費用が無駄になってしまう可能性があります。
大容量の製品は高額で、コンパクトなものに比べて100万円以上の差がつくケースもしばしば。このため、使用する電力を計算して、必要な容量を見極めることが大切です。
蓄電池のサイズ
蓄電池の本体サイズは、大小さまざまです。
製品を選ぶ際には当然、設置したいスペースに収まるかの確認が欠かせません。
設置できる大きさの製品をリストアップしてから、他の要素を検討すると良いでしょう。
現在はコンパクトなのに大容量を実現した製品や、狭い場所にも設置できる省スペースタイプも登場しています。なお、蓄電池には屋内用と屋外用があるので、気を付けて下さい。
蓄電池の想定寿命(サイクル数)
サイクル数は、何度まで充放電が可能かを示す値で、どれだけ長く蓄電池を使えるかの目安になります。
電池残量がない状態からフル充電し、全部使い切るまでが1回のサイクルです。
蓄電池に使われるバッテリーは充放電を繰り返すうちに劣化し、保証されたサイクル数を超えたあたりから、性能が落ちてきます。
サイクル数からは、大まかな耐用年数が判断できるので要注目のポイント。高額な製品でもサイクル数が多ければ、費用対効果で有利になります。
蓄電池の停電時出力
停電時でも電気を使えるのが、蓄電池の大きなメリットの一つです。
電力会社からの供給が止まっても、貯めていた電気を使用できます。災害時の対策や、常に空調が欠かせない場合などを考えると、停電時に電気が使えるのは安心です。
電気の供給がなくなった後、どれだけ電気を使えるのかは停電時出力によって決まります。
停電時出力が低いと、使える電化製品の大きさや数に制限が出てくるため、必要な性能を見極めましょう。
蓄電池の保証内容
メーカーによって、蓄電池の保証内容は違っています。
保証期間内なら、蓄電池ユニットなどの機器類にトラブルが発生した場合、無償で修理可能です。
機器の故障の他、電池容量が低下した場合にも対応があります。
具体的には、数年から15年くらいの保証が付いていることが多いでしょう。
メーカーごとに対応できる範囲や、保証制度を利用するための条件が細かく決まっているので、入念にチェックしておくことが大切です。
また、メーカーだけではなく設置工事を行う会社も、独自に保証を設けていることがあります。
工事に問題があった時の安心感が違うため、必要な保証がしっかり用意されているか確認して下さい。
太陽光発電との互換性<
太陽光発電と蓄電池は相性抜群で、電気代の抑制や停電時の発電能力など、多彩なメリットが生じます。ただし、注意したいのは太陽光発電システムの機器類との互換性があるかどうかです。特に太陽光発電を導入済みの場合、新しく購入した蓄電池と連結できるか確かめる必要性があります。他社製品同士でも問題ないケースもありますが、残念ながら未対応の製品も見られるので注意が欠かせません。
互換性については、同じメーカーで揃えるのが一手です。きちんと動作確認が行われているため安心して接続できますし、性能もフルに活かすことができます。また、同じメーカーだと問い合わせもスムーズです。太陽光発電システムと相性の良い蓄電池についてなど、何か相談したい時に役立つでしょう。
蓄電池と太陽光発電のセット購入によるメリットデメリット
家庭用蓄電池メーカー7社を比較
蓄電池を選ぶ際のポイントをチェックした所で、今度はメーカー各社の特徴を見ていきましょう。
特に蓄電池に関しての実績が豊富な、信頼感のある有名メーカーを7社厳選して紹介していきます。
それぞれに異なる魅力があるので、自身にとって最適なメーカーを選ぶためには、各社の情報をリサーチして比較することが大切。
以下では、それぞれのメーカーの長所やおすすめポイントについて、わかりやすくまとめていきます。
Panasonicの蓄電池
Panasonicは蓄電池のラインナップが豊富で、設置場所や生活スタイルに応じた製品を選べるのが特徴です。
屋内・屋外共に設置でき、容量も多彩。製品のバリエーションは、業界最多とも言われています。
しかも、複数の蓄電池を組みわせれば、驚きの大容量も実現可能。一般家庭はもちろん、店舗併用住宅にも対応します。
蓄電池の本体サイズはコンパクトですが、サイズの割には容量が大きいのもメリット。無理なく設置できて、たっぷりと電気を使えます。
他に、独自に開発した創蓄連携システムがあるのも特筆点でしょう。
これは、太陽光発電で作った電気を、自家消費と蓄電池の充電に活用できるシステムです。
これによって停電時でも自由に電気を使いながら、蓄電池に貯めることができます。更に、蓄電池に関しては、60%の出力保証が付くのも嬉しいポイント。
しっかりとアフターケアがあるので、長期間安心して使えます。
SHARPの蓄電池
蓄電容量の選択肢が多いのは、SHARPの特徴です。
小型から大型まであるため、ニーズにあわせて最適な一台を見つけられるでしょう。
しかも、COCORO ENERGYと呼ばれる見守りシステムを導入しており、AIなどのIT技術を使って、蓄電池の運転を最適化できるのが特徴です。
例えばAIは電気の使用状況を学習して、最適なエネルギーマネジメントを行います。
コントロールユニットは雷注意報などの気象データを受信し、災害に備えることも可能です。他にはIoT機器との接続も可能など、先進的な取り組みがあります。
ちなみにSHARPは、6.5kWhの全負荷モデルを2台連結して、13.0kWhまで容量をアップ可能。不足だと感じたら、後から増設することもできます。
オムロンの蓄電池
オムロンの蓄電池は単機能型と、ハイブリッド型の両方が用意されています。
さらに、ハイブリッド型は特定負荷型と全負荷型をラインナップ。合計すると、3タイプから最適なモデルを選択可能です。
それぞれのタイプによって、必要となる設置スペースの大きさや太陽光発電システムとの相性、停電時の使い勝手などが違うため、多彩なニーズに柔軟に対応できます。
太陽光発電を導入して間もない場合も、すでに10年以上経過してそろそろ寿命と言う時にも、最適な蓄電池を選べるわけです。
狭小スペースにも設置できる小型製品や、海岸近くのエリアでも安心の塩害対応モデルがあるのも魅力でしょう。
Nichiconの蓄電池
IT技術との親和性が高く、信頼性や便利さが大きく進化しているのがNichiconの特徴です。
まず、24時間365日の遠隔エラー監視サービスがあるため、異常を早期発見できるのはメリットでしょう。
蓄電池は10年以上使うこともあるので、常にコンディションをチェックしてくれるのは安心材料。メンテナンスやファームウェアのアップデートにも役立ちます。
また、AIを搭載しているため効率的に充電してくれるのも特徴です。
気象情報や家庭の電力使用状況を分析し、最適な自動運転を行います。
他には、電気自動車のバッテリーを使う、V2Hと連携できるのも魅力。V2Hからの電力と、蓄電池の電気を併行して利用できます。
長州産業の蓄電池
長州産業は、単機能型の他、ハイブリッド型(特定負荷と全負荷)の合計3種類を用意しています。
太陽光発電と組み合わせたい方から、コストをかけずに蓄電池だけ設置したい場合まで、幅広いニーズに対応できるのが長所です。加えて、長州産業の製品には、3種類の運転モードが用意されています。
モードを選ぶことで、売電を優先したり停電に備えたりと、状況に応じた使い分けが可能。
普段は発電した分を積極的に売って、台風が近づいたら停電に備えると言う具合に、柔軟な使い方ができます。固定価格買取制度(FIT)の実施中はもちろん、終了後に適したモードもあるのは特筆点でしょう。
ダイヤゼブラ電機の蓄電池
ダイヤゼブラ電機(田淵電機)は人気モデルのアイビス7を開発したメーカーです。アイビス7は2台連結時には約14kWhへの大容量化ができ、しかも、保証サイクル数が多いので長寿命なのも魅力。サイクル数は12,000回と、平均的な製品を上回っています。
耐用年数が長くなりますから、その分は費用対効果も優秀です。
更にダイヤゼブラ電機(田淵電機)の特徴として、1日に2サイクル可能なのは大きなポイントでしょう。
1日に2回充電できますから、小型の蓄電池でもたっぷりと電気を使えます。
京セラの蓄電池
住宅用太陽光のパイオニアとして知られる京セラは、実績が豊富な分、信頼感があるメーカーです。
長年かけて培ってきた品質管理と充実した保証制度は、蓄電池にも受け継がれています。
京セラの蓄電池は機能性が高く、保証期間は長めで、自然災害にも対応があるのは大きなメリットです。
また、大手ならではの卓越した技術力も見逃せません。
特にクレイ型リチウムイオン蓄電池を世界で初めて実用化したEnerezzaは、大きな話題になりました。
Enerezzaに搭載されたクレイ型リチウムイオン蓄電池は、電極材料を粘度状にすることで寿命や安全性の向上、
コストダウンを実現しています。
現在、Enerezzaには3種類の蓄電容量がラインナップされているので、気になった方はチェックしてみましょう。
構造内部はセパレート型になっていて、火災に強いのも魅力です。
蓄電池の価格相場と性能比較の詳細はこちら
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
施工店の選びかた
良いメーカーやモデルを選んでも、施工が不適切だと本来の性能を発揮できず、発電効率の低下やトラブルの原因になる可能性があります。中には手抜き工事や不正を行う業者も存在するため、施工店選びをおろそかにしてはいけません。
信頼できる施工店を選ぶ意義
施工の質は太陽光発電システムの寿命や安全性を左右します。さらに、設置後に発生するかもしれない故障や不具合へのサポート体制が整っているかどうかも重要な判断基準です。安心して長く利用するためには、信頼性の高い施工店に任せることが欠かせません。
施工店選びで意識したいポイント
施工実績や口コミ、アフターサポートの内容、保証制度の有無などをしっかり確認することが大切です。また、メーカーから認定を受けているかどうか、施工資格を持ったスタッフが対応しているかも信頼性を判断する材料となります。
暮らしにマッチした蓄電池を紹介してくれる
蓄電池はメーカーによって、機能や価格の他、保証内容が大きく違っています。
このため、色々な選択肢の中から、最適な蓄電池を選んで紹介してくれる施工店を選ぶことが大切です。
ライフスタイルや導入目的によって、相応しい蓄電池は変わってきます。
蓄電池を熟知していて、適切な容量や性能を見極められる業者でなければ、最適な一台を選ぶのは難しいでしょう。
相談の際には、しっかりとヒアリングした上で、ぴったりの製品を探してくれるかどうか確かめて下さい。こちらの話を聞かずに営業トークを繰り返すようだと、信頼はできません。
扱えるメーカーやモデルが幅広い施工店を選ぶのもポイントです。
施工店は幅広いメーカーの製品を扱えるケースもあれば、逆に1社か2社に絞って紹介していることもあります。
前者は選択肢が広く、多彩なニーズに応えられる点が強みです。
実績があり信頼できる
高価な蓄電池も、手抜き工事で設置した場合には性能をフルに発揮できません。
異常が生じたり、寿命が縮んだりする可能性もあります。
よって、設置を任せる施工店は、実績と信頼について充分なチェックが必要です。
実績が豊富な会社は、これまで真っ当な経営を行ってきたと考えられます。
不正や違法行為をすると行政処分の対象になりますし、評判が悪いとネットに書き込まれたりして、長く経営を続けられないためです。
したがって、長期間にわたって多数の実績がある施工店は、信頼性は高いと言えるでしょう。
なお、気になった施工店があったら、ネットで口コミを探してみると参考になります。
アフターフォローが充実している
蓄電池はメーカー独自の保証の他に、施工店が追加でアフターフォローを用意している場合があります。
例えば、本体の保証はメーカーが受け持ち、工事によるトラブルは施工店が対応するような形です。
もちろん、施工店のアフターフォローは充実しているに越したことはありません。
価格とのバランスも大切ですが、メンテナンスや緊急時の対応を考えると、必要十分なアフターフォロー体制があると安心に繋がります。
メーカー選びに迷ったら信頼できる施工店に相談してみよう
蓄電池はメーカーやモデルによって様々な特徴があるため、中々、候補を絞り切れないケースも珍しくありません。
迷った時には、信頼できる施工店に相談すると、解決の糸口が見つかるはずです。
エコ発電本舗は業界最安値を目指しながら、メーカーが推奨している施工店だけと提携し、高品質を確保しています。地域密着型で、工事後のトラブルなども短時間で対応可能。
この機会に、蓄電池の無料見積もりをしてみてはいかがでしょうか。
蓄電池の業界最安価格の見積りはこちら