
太陽光は戸建て専用ではなくなった
「太陽光発電は持ち家の人だけのもの」——長らくそう思われてきましたが、2025年現在、その常識は大きく変わりつつあります。マンションや賃貸住宅でも太陽光発電のメリットを享受できる、新しい導入スタイルが次々と登場しているのです。
集合住宅に住む人、賃貸物件に住む人、初期投資ができない人——これまで太陽光発電を諦めていた多くの人々に、新たな選択肢が広がっています。
「所有」から「利用」へのパラダイムシフト
従来の太陽光発電は、自分でパネルを購入・設置し、所有することが前提でした。しかし新しいモデルでは、「所有せずに利用する」「共有して使う」という発想で、より多くの人が太陽光発電にアクセスできるようになっています。
屋上シェア、PPAモデル、バーチャルPPA、コミュニティソーラー——こうした新しい仕組みが、太陽光発電の普及を加速させています。
この記事で紹介する4つの新スタイル本記事では、マンションや賃貸でも導入可能な太陽光発電の新しい形を4つ紹介します。それぞれの仕組み、メリット・デメリット、向いている人を詳しく解説していきます。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
屋上シェア型:マンション住民で太陽光をシェア

屋上シェア型は、マンションの屋上や屋根に太陽光パネルを設置し、その発電電力を建物全体で共有利用する仕組みです。共用部分の電力として使用したり、各戸に按分して供給したりするモデルがあります。
管理組合が主体となって導入を決定し、住民全体で費用を負担する形が一般的です。大規模なマンションほど、スケールメリットが大きくなります。
共用部の電気代を大幅削減
エレベーター、廊下の照明、エントランスの照明、給水ポンプ、機械式駐車場——マンションの共用部では、意外と多くの電力を消費しています。月額で数十万円の電気代がかかっている大型マンションも珍しくありません。
屋上シェア型太陽光発電を導入すれば、この共用部の電気代を30〜50%削減できる可能性があります。削減された電気代は管理費の軽減につながり、全住民にメリットがあります。
各戸への直接供給モデルも登場
最近では、屋上で発電した電力を各住戸に直接供給し、各家庭の電気代を削減するモデルも登場しています。専有部分で使用した太陽光電力の分だけ、電気料金が安くなる仕組みです。
このモデルでは、発電量を住戸数で按分したり、電力使用量に応じて配分したりと、様々な方式があります。公平性を保つための仕組み作りが重要です。
導入のハードルは管理組合の合意
屋上シェア型の最大のハードルは、管理組合での合意形成です。多くのマンションでは、区分所有者の過半数または3分の2以上の賛成が必要になります。
初期費用の負担方法、メリットの配分方法、メンテナンス責任——これらを明確にし、住民全体が納得できる計画を立てることが成功の鍵です。
太陽光発電が向いているマンション
築年数が比較的新しく、屋上の構造が太陽光設置に適している。住戸数が多く、スケールメリットが出せる(50戸以上が目安)。管理組合が活発で、合意形成がしやすい。共用部の電気代負担が大きい——こうした条件に当てはまるマンションでは、屋上シェア型が非常に有効です。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
PPA(第三者所有)モデル:初期費用ゼロで太陽光導入

PPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)モデルとは、第三者である発電事業者が太陽光発電システムを所有・設置し、発電した電力を建物所有者や入居者に販売する仕組みです。
利用者は初期費用を負担せず、使用した電力分だけを事業者に支払います。いわば「太陽光発電のリース・レンタル」のような形態です。
初期投資ゼロが最大のメリット
PPAモデルの最大の魅力は、初期投資が一切不要なことです。数百万円の設備投資をすることなく、すぐに太陽光発電のメリットを享受できます。
賃貸物件のオーナー、予算が限られている法人、資金を他の投資に回したい個人——様々な立場の人にとって、資金的ハードルがないのは大きなメリットです。
電気料金は通常より安く設定
PPA事業者から購入する電力の単価は、通常の電力会社から購入するより5〜20%程度安く設定されるのが一般的です。初期費用ゼロで、なおかつ電気代も安くなるという、二重のメリットがあります。
例えば、通常30円/kWhの電気代が、PPAモデルでは25円/kWhで購入できれば、月間400kWh使用する家庭で月2,000円、年間24,000円の節約になります。
メンテナンスも事業者が負担
設備の所有者はPPA事業者ですから、メンテナンス、修理、保険などの費用や手間もすべて事業者が負担します。利用者は何の心配もなく、発電された電気を使うだけです。
故障やトラブルが発生しても、利用者には金銭的負担が発生しません。この「リスクフリー」な点も、PPAモデルの大きな魅力です。
契約期間終了後の選択肢
PPA契約の期間は通常10〜20年です。契約期間終了後は、いくつかの選択肢があります。
設備を無償または格安で譲り受ける、契約を延長して引き続き利用する、設備を撤去してもらう——事業者や契約内容によって異なりますが、多くの場合、契約終了後に設備を譲り受けられるプランが用意されています。
太陽光発電が向いている人・物件
初期投資を避けたい人、賃貸物件のオーナー(入居者へのアピールポイントになる)、法人・事業者(キャッシュフローを重視する場合)、メンテナンスの手間を避けたい人——こうしたニーズを持つ方にPPAモデルは最適です。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
バーチャルPPA:物理的設置なしで太陽光電力を購入
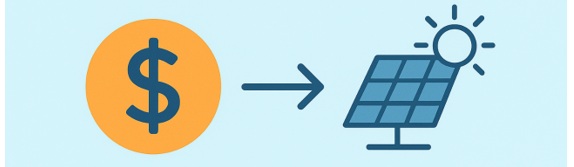
バーチャルPPA(VPPA)は、物理的に自分の建物に太陽光パネルを設置することなく、遠隔地にある太陽光発電所で発電された電力を「購入」する契約形態です。
実際の電力は通常通り電力会社から供給されますが、契約上は太陽光発電所からの電力を購入したことになり、再生可能エネルギー利用の実績として計上できます。
マンションや賃貸でも「太陽光ユーザー」になれる
自分の住む建物に太陽光パネルを設置できない人でも、バーチャルPPAを利用すれば「太陽光発電の電力を使っている」ユーザーになれます。
物理的な制約がないため、マンション住民、賃貸住宅の入居者、屋根が狭い・方角が悪いなどの理由で設置が難しい人でも利用可能です。
企業の脱炭素目標達成にも活用
バーチャルPPAは、企業や法人が脱炭素目標を達成するための手段としても注目されています。RE100(事業で使用する電力を100%再生可能エネルギーで賄う国際イニシアティブ)への対応などに活用されています。
自社ビルに太陽光を設置できない企業でも、バーチャルPPAを通じて「再エネ100%」を実現できるのです。
価格は市場連動型が多い
バーチャルPPAの電力価格は、市場価格と連動する形で設定されることが多いです。電力市場価格が下がれば支払額も減り、上がれば支払額も増えるという仕組みです。
ただし、長期契約により価格を固定できるプランもあり、電力価格の変動リスクをヘッジする手段として活用できます。
まだ発展途上のサービス
バーチャルPPAは欧米では普及が進んでいますが、日本ではまだ発展途上のサービスです。提供する事業者も限られており、個人向けのプランは少ないのが現状です。
しかし、今後の普及拡大が期待されており、将来的にはより手軽に利用できるようになると予想されています。
向いている人・組織
物理的に太陽光設置ができないが、再エネ利用実績が欲しい人、脱炭素経営を目指す企業、環境意識が高く、再エネ利用にこだわりたい人——こうしたニーズを持つ方に向いています。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
コミュニティソーラー:地域で太陽光をシェア

コミュニティソーラーとは、地域住民や企業が共同出資して太陽光発電所を建設・運営し、発電された電力や収益を参加者で分配する仕組みです。
公共施設の屋根、遊休地、学校の屋上など、地域内の適地に太陽光パネルを設置し、地域全体で活用します。
少額から参加できる「市民ファンド」型も
大規模な太陽光発電所を個人で建設するのは困難ですが、コミュニティソーラーでは1口数万円〜数十万円の少額出資から参加できます。
多数の参加者で費用を分担するため、個人の負担は小さく抑えられます。投資としての側面と、地域貢献・環境貢献の側面を併せ持つのが特徴です。
発電量に応じた配当を受け取れる
出資した金額に応じて、発電所の発電量や売電収入から配当を受け取れます。年利2〜5%程度の配当が期待できるプロジェクトが多く、預金よりも高い利回りが見込めます。
また、一部のプロジェクトでは、配当を電気料金の割引として受け取れる仕組みもあります。
地域のエネルギー自給率向上に貢献
コミュニティソーラーは、単なる投資商品ではなく、地域のエネルギー自給率を高め、災害時のレジリエンスを強化する社会的意義があります。
地域で発電した電力を地域で消費する「地産地消」のエネルギーモデルは、送電ロスの削減や、災害時の電力確保にもつながります。
参加者同士のコミュニティ形成
コミュニティソーラーのプロジェクトでは、参加者同士の交流イベントや、発電所の見学会、環境学習プログラムなどが開催されることもあります。
同じ志を持つ人々とのつながりが生まれ、地域コミュニティの活性化にも寄与します。
コミュニティソーラーが向いている人
少額から太陽光発電に投資したい人、地域貢献・環境貢献に関心がある人、自宅には設置できないが太陽光に関わりたい人、預金より高い利回りの投資先を探している人——こうした方々にコミュニティソーラーは魅力的な選択肢です。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
新スタイル導入時の注意点

契約内容を十分に確認する
PPAモデルやバーチャルPPAなど、新しい契約形態では、従来の太陽光発電とは異なる契約条件が設定されます。契約期間、料金体系、中途解約の条件、契約終了後の設備の扱い——これらを事前にしっかり確認しましょう。
特に、長期契約になることが多いため、将来的な状況変化(引越し、建物の売却など)も想定して検討することが重要です。
事業者の信頼性を見極める
新しいビジネスモデルには、新規参入事業者も多く存在します。事業者の経営基盤、実績、サポート体制などを確認し、信頼できる事業者を選びましょう。
事業者が倒産した場合の設備の扱いや契約の継続性なども、事前に確認すべきポイントです。
経済効果を正確にシミュレーション
「初期費用ゼロ」「電気代削減」といったメリットは魅力的ですが、具体的にどれだけの経済効果があるのかを、数字で確認することが重要です。
自分の電力使用パターン、料金プラン、契約条件を踏まえて、シミュレーションしてもらいましょう。複数の事業者やプランを比較することも大切です。
賃貸の場合は大家・管理会社の許可を
賃貸物件でPPAモデルなどを利用する場合、建物に設備を設置することになるため、大家や管理会社の許可が必要です。
事前に相談し、書面で許可を得ておくことでトラブルを防げます。退去時の設備撤去についても、あらかじめ取り決めておきましょう。
コミュニティソーラーは出資リスクも考慮
コミュニティソーラーへの出資は、一種の投資です。発電量が想定を下回る、事業がうまくいかないなどのリスクもゼロではありません。
プロジェクトの事業計画、収支見通し、リスク説明をしっかり確認し、余裕資金の範囲内で参加することをお勧めします。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
まとめ:太陽光は誰でもアクセスできる時代へ

マンション住まい、賃貸住宅、初期投資ができない——こうした理由で太陽光発電を諦めていた方々にも、今は様々な選択肢があります。
屋上シェア、PPA、バーチャルPPA、コミュニティソーラー——自分の状況に合った方法を選べば、誰でも太陽光発電のメリットを享受できる時代になったのです。
所有から利用へ、シェアリングの時代
太陽光発電も、車や住宅と同様に「所有」から「利用」「シェア」へとパラダイムシフトしています。必ずしも自分で設備を所有しなくても、太陽光のメリットを受けられる仕組みが整いつつあります。
この流れは今後さらに加速し、より多様で柔軟な選択肢が登場すると予想されます。
まずは情報収集から始めよう
新しいサービスは日々登場しています。まずは、自分の住む地域や建物で利用可能なサービスがないか、情報収集から始めてみましょう。
自治体の環境部門、地域の電力会社、太陽光発電事業者などに問い合わせることで、具体的な情報が得られます。
環境にも家計にもメリットのある選択を
太陽光発電は、環境負荷を減らしながら、家計にもメリットをもたらす一石二鳥の選択です。持ち家でなくても、予算が限られていても、あなたに合った方法が必ずあります。
新しい太陽光発電のスタイルを活用して、持続可能で経済的な暮らしを実現しましょう。





























