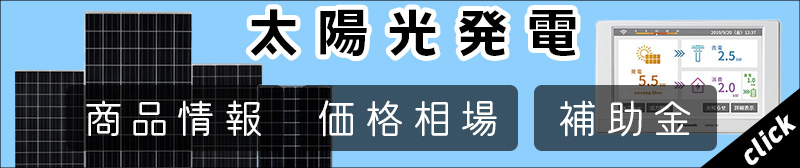太陽光発電システムは、国が推奨している将来性の高い再生可能エネルギーの一つです。自然の力(太陽光)を利用して電力を作ることができるため、環境に配慮しながら生活に必要なエネルギーを創出できる点に魅力があります。「我が家でも太陽光発電システムの導入を検討中だけど、性能や価格のことなど詳しく学んでおきたい」という人もいるかもしれません。
この記事では、太陽光発電システムの仕組みや価格、メリット・デメリットを解説しました。多岐にわたる論点をピックアップしてポイントをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
太陽光発電の今年度の売電価格について
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
ソーラーパネルの価格と性能

性能によって異なるソーラーパネルの価格相場
太陽光発電システムにおいて、最も目に触れるのがソーラーパネルです。発電量や耐久性を左右する主要な部品であり、その価格はパネル導入費用の大部分を占めます。価格は「パネル1枚あたり」あるいは「1kWあたり」で表されるのが一般的です。
ソーラーパネルの価格相場
直近のデータによると、パネル1枚あたりの価格は20万円〜30万円程度(出力250W~400W)、1kWあたりでは約15万円前後が相場とされています。価格は製品の性能や品質、設置環境、さらには需要と供給の動向によっても変動するため、一律ではありません。
住宅用太陽光発電システムの費用目安
一般的な住宅用の太陽光発電システムは、容量3〜5kWが標準的です。これを相場に当てはめると、ソーラーパネルの費用は「1kWあたり15万円×3〜5kW=45万円〜75万円」となります。もちろん、実際には工事費用やパワーコンディショナーなどの周辺機器の費用も加わりますが、パネル価格の目安を把握しておくことは、導入を検討する上で大切です。
ソーラーパネルの「性能」とは?
太陽光発電システムにおける性能は、大きく分けて「発電能力」と「変換効率」で評価されます。
発電能力(出力)
発電能力とは、ソーラーパネルがどれだけの電力を生み出せるかを示す指標です。これは、パネル1枚あたりの定格出力(W数)と設置枚数によって決まります。例えば、1枚あたり300Wのパネルを30枚設置した場合、300W×30=合計9kWの発電能力となります。
変換効率
変換効率は、太陽光として受けたエネルギーをどの程度電力に変換できるかを示す割合です。国内で販売されているソーラーパネルの平均的な変換効率は15%〜20%程度とされています。変換効率が高ければ、同じ面積でもより多くの電力を生み出せるため、限られた屋根スペースを有効に活用できるという利点があります。
性能評価のポイント
ソーラーパネルを選ぶ際には、単純な出力(kW)だけでなく、変換効率や設置環境との相性を考慮することが重要です。高効率パネルを導入すれば、省スペースで発電量を確保でき、長期的な収益性や電気代削減効果にもつながります。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
太陽光発電システムにおける設置費用の相場と変動要因
太陽光発電の設置費用とは、先述したソーラーパネルやその他の設備を設置したり工事したりするのにかかる費用です。住宅価格と施工費用が異なるように、太陽光発電システムの場合も、ソーラーパネルの価格と設置費用は別項目の費用となります。ここでは、その太陽光発電の設置費用の相場と変動要因をまとめました。
最新のデータに見る設置費用の相場
資源エネルギー庁(経済産業省)が太陽光発電について行った全国的な調査における最新のデータ(2023年12月)では、太陽光発電設備の1kWあたりの設備費用は22.7万円、工事費用が7.6万円となっています。設備費と工事費を合わせた導入費用の合計は1kWhあたり約30万円程度です。
設備費は、ソーラーパネルやパワーコンディショナー、架台といった機器類にかかる費用です。従って、この設備費を除いた純粋な工事費用すなわち設置費用は1kWhあたり7.6万円となります。一般家庭用の太陽光発電システムで多い3kW〜5kWで計算すると、設置費用は7.6万円×3kW/5kW=22.8万円〜38万円になります。
設置費用の変動要因
太陽光発電システムの設置費用相場の主な変動要因には以下3つがあります。
● ソーラーパネルの材料(種類)
● 設置場所(地域)
● 設備の規模
ソーラーパネルの材料(種類)
ソーラーパネルの材料には、結晶シリコン、薄膜シリコン、化合物系(CIGS系)パネルなどの種類があり、それぞれ相場が違います。主流は結晶シリコン系ですが、薄膜シリコンやGIGS系も一定のシェアを有しており、どれを採用するかで費用が変わってくるため、慎重に選ぶことが大切です。
設置場所(地域)
「設置場所」も相場を動かす要因の一つとなります。太陽光発電システムは、設置する地域によって気候条件が変わり、それに合わせて施工を工夫することになるため、設置場所によって費用が変化するのは必然です。例えば、積雪の多い地域では、通常より高い耐久性を付加する必要があるため、その分施工費が高くなります。また、日照時間の短い地域では、より変換効率が高い高性能のパネルを設置しなければなりません。その結果、コストアップにつながるでしょう。といった具合に、設置場所(地域)も設置費用相場の変動要因の一つです。
設備の規模
最後に、太陽光発電設備の「規模」が挙げられます。太陽光発電システムと一口にいっても、一般家庭向けから事業用・産業用レベルまで、設備の規模には大きな幅があります。畳一枚分から設置可能ですが、大規模になると1,000平方メートル以上の規模も設置可能です。規模が変化すると、導入するパネルの枚数も変わるため、それによって設置費用が変動するのは必然です。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
太陽光発電システムの設置にかかる費用の内訳
太陽光発電の設置にかかる費用は、大きく「設備費」「工事費」「諸経費」の3つに分類できます。最も大きな割合を占めるのは設備費で約60%、次いで工事費が約25%、残り15%が諸経費です。
・太陽光発電の導入にかかる費用の内訳
| 費目 | パーセンテージ |
|---|---|
| 設備費 | 約60% |
| 工事費 | 約25% |
| 諸経費 | 約15% |
設備費
太陽光発電システムの設置に必要な設備には、太陽光パネル、パワーコンディショナー、架台の3つがあります。とりわけ発電において重要な部品は太陽光パネルとパワーコンディショナーの2つです。設備費の平均的な単価相場(kWあたり/個あたり/台あたり)は40万円〜50万円程度です。
工事費
工事費は、太陽光発電システムの設置にかかる費用です。相場はありますが、実際の価格はメーカーや施工業者によって幅があります。平均的な単価相場は1kWhあたり7.6万円(2023年度)です。
諸経費
設備費、工事費以外でかかる費用はすべて諸経費として計上します。設置業者によって費目は変わりますが、一般的には手数料や消費税、補償費用、補助金の申請費用などが諸経費として有名です。費目や内訳が分かりづらいため、見積りの際によく確認する必要があります。平均的な単価相場は、1kWあたり3,000円〜です。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
太陽光発電システムの電気代削減効果の具体例

住宅用(個人宅)の節約事例
一般家庭用の太陽光発電では、売電や自家消費によって電気代を節約したりゼロにしたり、場合によってはプラスに変えることも可能です。
例えば、一般家庭用で多い3kWの太陽光発電システムを設置した場合、年間で約3,000kWhを発電することができます。一般家庭の年間消費電力量が平均で約5,500kWhとなっているため、これを前提にすると、太陽光発電設備導入の効果により、年間における必要電力の半分以上をまかなうことが可能です。
節約方法は売電か自家消費となりますが、現在は買取価格が下落し電気代も高騰しているため、売電より自家消費するほうがよりお得な節約ができます。
産業用(工場・事業所)での節約事例
産業用の場合も家庭用と要領は同じです。工場や事業所への太陽光発電システムの導入により、当該事業所の電気使用量を削減し、年間の電気代を大幅に節約することができます。効果は事例によってさまざまですが、ある施設では、太陽光発電設備の導入によって電気使用量を約10%削減し、年間の電気代を1,000万円節約することに成功しました。
企業における電気代は、必要経費のかなりの割合を占めており、電気代の高騰によって財政が圧迫し、収益が低下してしまうケースも少なくありません。その点を考慮すると、産業用として太陽光発電システムを導入することは、サイドビジネスというより、持続可能な企業経営を行うための重要な施策といえるでしょう。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
太陽光発電システムのメリット

太陽光発電システムを導入することには、以下のようなメリットがあります。
● 電気代を節約できる(0円になることも!)
● 余った電気を売ることができる
● 停電時にも電気が使える
● 住環境の質を向上できる
● 地球環境の保全に貢献できる
電気代を節約できる(0円になることも!)
太陽光発電システムを導入すると、ソーラーパネルで発電した電気を家庭内に供給して使うことができます。発電量が多ければ多いほど、電力会社から購入する電気量(買電量)が減って、電気代を削減することが可能です。
また、自家発電した電気は、自宅で使うだけでなく、余剰電力を電力会社に売ることができます。売電したお金は自分の収入となるため、売電量が増えれば増えるほど、電気代を節約するどころか0円ないしはプラスにすることも可能です。
余った電気を売ることができる
前に述べたとおり、自宅で発電した電気は、余ったら電力会社に売ることができます。しかも国が定めたFIT(固定価格買取制度)により、設置から10年間は固定価格で買い取ってもらえるため、売電収入が安定します。
直近のFIT価格は、家庭用(10kW未満)の太陽光発電システムにおいて、1kWhあたり15円(2025年度)です。精度開始時と比べると価格が下がっているため、現在は、売電するより自家消費したほうがお得になると言われています。
停電時にも電気が使える
太陽光発電システムは、災害時や停電時にも強みを発揮します。発災時、設備に故障や異常がなく、きちんと発電が出来ている状態であれば、昼間に関しては停電時でもそのまま電気を使うことができます。ただし、蓄電池やインバーターなど自立運転を可能とする必要機能を備えていることが条件です。
住環境の質を向上できる
太陽光発電設備は副次的なメリットとして、家の断熱効果を高めることができます。屋根にソーラーパネルを設置することで、自然と太陽光を断熱できるからです。夏場は、ソーラーパネルが太陽の熱を吸収して屋根の温度を下げ、冬場は、吸収した太陽熱の気密性が高まり余分な放出がおさえられ暖かくなります。
地球環境の保全に貢献できる
太陽光発電システムは、人間だけでなく、自然環境にも恩恵をもたらします。太陽光発電は自然にある太陽光というエネルギーを電気に変換する設備であるため、電気を作る際に何かを燃やして二酸化炭素(CO2)を排出することはありません。自然エネルギーを用いて、クリーンな方法で電気が作れる仕組みを構築した点が、太陽光発電の優れたメリットです。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
太陽光発電システムのデメリット

太陽光発電システムの導入にはメリットだけなく、以下のようなデメリットもあります。
● 初期費用とそれを回収する期間が必要になる
● 定期的なメンテナンスが必要になる
● 天気が悪い日は発電量が低くなる
● 屋根の状況によっては設置できないこともある
初期費用とそれを回収する期間が必要になる
太陽光発電システムは、長期的に運用することではじめて利益が出るようになります。導入時は設備の購入費や工事費など支出が多いため、すぐに利益を出すことはできません。長期的な運用を行い、初期費用の回収と利益を挙げていくための期間が必要になります。そしてそれをクリアするための資金計画が重要です。
定期的なメンテナンスが必要になる
太陽光発電システムは、一度導入したら終わりではありません。長期にわたって性能を維持しながら利益を出し続けるためには、計画的かつ定期的なメンテナンスが必要です。全体的な点検を行ったり、消耗・故障部品を交換したり、設備周りの清掃をしたり、風雨などで劣化した設備を補修する必要性も生じます。
太陽光発電システムの安定運用を続けるためには、設備のクオリティを保つことが大切です。そのためにメンテナンスを行うことが重要となります。
天気が悪い日は発電量が低くなる
太陽光発電システムでは、太陽の光をエネルギーに変換して電気を作りだしています。晴天の日が続くと発電量も多くなりますが、逆に天候の悪い日(日照時間が短い)が続くと発電量が少なくなり、高い効果を挙げることができなくなります。また天候が正常でも冬場は日照時間が短くなるため、夏と比べて発電量が低下する可能性が高いです。もちろん夏でも冬でも「夜間」は発電自体ができません。
屋根の状況によっては設置できないこともある
ソーラーパネルは、屋根があればどこでも設置できるわけではありません。屋根の向き、面積、材質、強度、築年数、構造など、条件が整わない場合は設置できない可能性があります。新築の場合は太陽光発電の設置を前提に設計を行うことができるため、リスク回避がしやすいのですが、既存の住宅に導入する場合は、本当に設置が可能かどうか事前の調査が必要です。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
太陽光発電のメンテナンスと耐用年数について
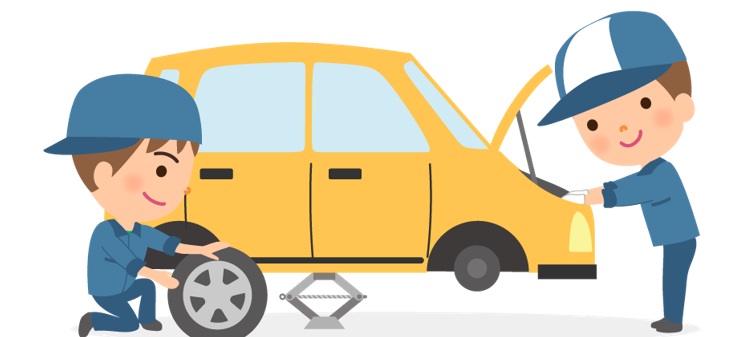
太陽光発電の初期費用は約64万円~約90万円
太陽光発電システムの初期費用は、一般的な家庭用の太陽光発電設備(3kW〜5kW)の場合で約64万円〜約90万円が大体の相場となっています。費用の内訳は、設備費・設置費・諸経費で構成され、それぞれの初期費用の相場は、設備費(ソーラーパネル・パワコン・架台・その他)が40万円~50万円程度、設置費(工事費)は23万円~38万円程度、諸経費は9.000円~15,000円程度です。
・太陽光発電(3kW〜5kW)の初期費用
| 費目 | 相場の目安 |
|---|---|
| 設備費 | 約40万円~約50万円 |
| 工事費 | 約23万円~38万円 |
| 諸経費 | 9千円~1万5千円 |
太陽光発電システムにおける投資回収とは、上記の費用につき回収していく作業を指し示しています。
投資回収期間は10年前後が目安
太陽光発電システムの投資回収期間は一律に決められるものではなく、投入した費用や設備規模によって大きく変わります。住宅用の場合は10年未満での回収が可能なケースもありますが、規模の大きな産業用では10年以上を要することも珍しくありません。つまり、太陽光発電は短期的な収益を狙うものではなく、長期的な視点で取り組むべき投資だといえます。
「10年」が目安とされる理由
では、なぜ一般的に「10年前後」が回収期間の目安とされるのでしょうか。その背景にあるのが、FIT(固定価格買取制度)です。この制度では、太陽光発電で生み出した電気を一定期間、国が定めた固定価格で電力会社が買い取ります。住宅用(10kW未満)の場合は10年、産業用(10kW以上)は20年の期間が設定されており、少なくともその期間は安定した売電収益を得られるのが特徴です。
安定収益が投資計画を支える
FIT制度を活用すれば、投資計画において確実に見込める収益があるため、住宅用であれば「約10年」、産業用なら「10年以上」という見通しが立ちます。この安定収益こそが、太陽光発電の投資回収期間の目安が「10年前後」とされる根拠となっています。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
太陽光発電システムのメンテナンスと耐用年数について
メンテナンスの「メイン」はパワコンとモジュール(パネル)
太陽光発電のメンテナンスの基本
太陽光発電システムのメンテナンスで中心となるのは、「パワーコンディショナー(パワコン)」と「モジュール(パネル)」の2つです。どちらも耐久性が高く長寿命ではありますが、経年劣化や自然災害によって故障や破損が発生することがあります。長期間の使用で発電能力が徐々に低下していくため、適切な修理や部品交換を行うことが大切です。
パワーコンディショナーのメンテナンス
パワコンは、太陽光パネルでつくられた直流電力を交流に変換する重要な機器です。トラブルの原因で多いのは、内部フィルターにゴミやホコリが溜まり、目詰まりを起こすケースです。そのため、定期的な清掃と点検を行うことが推奨されます。また、ヒューズが切れた場合は必ず専門業者に交換を依頼し、自己判断での作業は避けましょう。
モジュール(パネル)のメンテナンス
ソーラーパネルは屋外に設置されるため、自然災害による破損や汚れが発生しやすい部分です。特に台風や豪雨による破損、鳥の糞や落ち葉の堆積による発電効率の低下がよく見られます。簡単な目視点検で異常を確認することは可能ですが、正確な状態を把握するためには、専用の測定機器を用いた数値診断が必要になります。
長く使うために
太陽光発電システムを長期間安定的に運用するには、定期点検や清掃を欠かさず行い、異常が見られた場合には早めに専門業者に相談することが重要です。適切なメンテナンスを継続することで、システムの寿命を延ばし、投資効果を最大限に引き出すことができます。
太陽光発電システムの法定耐用年数は「17年」
太陽光発電システムを効果的に運用するには、「耐用年数」を理解しておくことが欠かせません。耐用年数とは、設備を資産として利用できる期間を指します。例えば、10年間使用できるなら耐用年数は10年、20年なら20年という形です。
法定耐用年数は17年
太陽光発電システムの法定耐用年数は「17年」と定められています。これは会計処理上の目安であり、減価償却を行う際に基準となる期間です。つまり、会計上の資産処理をする際には、この17年を基準にしなければなりません。
実際の耐用年数はもっと長い?
一方で、実際の設備寿命は製品や設置環境によって異なります。適切にメンテナンスを行えば30年近く稼働するケースもあれば、20年程度で寿命を迎える場合もあります。つまり、法定耐用年数と実際の稼働年数は必ずしも一致するわけではありません。
計画立案の目安
整備計画や保全計画を立てる際には、まずは法定耐用年数である17年を基準としつつ、実際の耐用年数が前後する可能性を考慮することが重要です。定期点検や部品交換を組み合わせながら、長期的な視点で設備を管理すれば、投資効果を最大限に引き出せるでしょう。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
太陽光発電システムのランニングコスト
太陽光発電のランニングコストと一口にいっても、費用は住宅用と産業用で異なります。それぞれのランニングコストをリサーチしましたので、チェックしてみましょう。
「住宅用」のランニングコスト
太陽光発電システムにおける「住宅用」のランニングコストは、経済産業省が発表した「令和4年度以降の調達価格等に関する意見」によると、「1kWあたり3,000円(年間)」です。3kWの設備なら年間9,000円、5kWなら年間約15,000円となります。費用の内訳は定期点検費用や故障時の修理代、部品交換代、清掃費用などです。
「産業用」のランニングコスト
太陽光発電システムにおける「産業用」のランニングコストは、経済産業省発行の同「令和4年度以降の調達価格等に関する意見」によると、2023年度の想定値として、「1kWあたり5,000円(年間)」となっています。10kWの設備なら年間約5万円、20kWなら年間約10万円のランニングコストが必要です。費用内訳は、定期点検費用、日常運転管理、除草作業、修理代、保険料、地代などがあります。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
太陽光発電システムのFIT制度と売電価格
投資の目的で太陽光発電システムを導入する場合は、国が実施しているFIT(固定価格買取制度)を活用することができます。ここでは、FITの概要とメリット、売電価格についてまとめました。
FIT(固定価格買取制度)の概要とメリット
FIT(固定価格買取制度)とは、再生可能エネルギーの普及を目的として国が行っている政策の一種です。太陽光、風力、水力など再エネの種目ごとに、国が定めた価格で一定期間、余剰エネルギーを買い取ってもらうことができます。太陽光発電の場合は、10kW未満で10年間、10kW以上で20年間の買取が保証されています。
FIT制度のメリットは、価格変動リスクを避けられることです。FIT価格は市場取引を通じたものではないため、市場価格の変動に関係なく、常に一定の価格で売電をすることができます。そのため、投資を目的に太陽光発電を導入する際の収益見通しを立てやすいのがメリットといえるでしょう。
FITにおける売電価格とその推移
太陽光発電投資で最も注目されるポイントの一つが「売電価格」です。価格が固定されることで収益の安定性は確保されますが、その単価が低ければ投資効果も小さくなります。2024年時点でのFIT価格は 1kWhあたり16円 です。この価格で契約すれば、導入から10年間は同じ単価で売電できます。
年間売電収入の試算
具体的な収益をイメージするために、システム容量5kWを例に試算してみましょう。
計算式:
売電収入(年間)=売電価格 × 年間発電量(1,000kWh/kW) × システム容量
これを当てはめると、
16円 × 1,000kWh × 5kW = 80,000円
つまり、5kWシステムでは年間約8万円の売電収入が見込めます。
FIT価格の推移
FIT制度が始まった2009年当初、売電価格は1kWhあたり48円(10kW未満)と高単価でした。その後は年を追うごとに引き下げられ、42円、38円、37円、33円、31円、30円…と低下し、2024年には16円となっています。
売電よりも自家消費の時代へ
FIT価格が低下する一方で、電力会社から購入する電気料金は上昇し、現在では1kWhあたり30円前後となっています。そのため、売電よりも 自家消費を優先する方が経済的に有利 という状況です。日中の発電を家庭で活用し、余剰分を蓄電池や電気自動車に蓄えることで、電気代削減効果を最大化できます。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
太陽光発電システムの確定申告と固定資産税
太陽光発電システムの投資・運用では、税金も関係してきます。ここでは、太陽光発電において確定申告が必要になるケースとそうでないケース、固定資産税の課税対象となる場合とそうでない場合、さらにその税額計算について紹介します。
太陽光発電で「確定申告」が必要な人・必要でない人
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を集計し、税務署に申告して納税額を確定する手続きです。太陽光発電システムを導入して余剰電力を売電している場合、その収入が一定額を超えると確定申告の対象になります。
会社員の場合
会社員の方が太陽光発電で収入を得た場合は、「給与所得以外の所得」が20万円を超えるかどうかが判断基準になります。売電収入から必要経費を差し引いた所得が20万円を超えると、確定申告が必要です。逆に20万円以下であれば、確定申告は不要です。
個人事業主の場合
個人事業主は、売電収入も事業収入の一部として扱います。そのため、売電収入を含めた総所得額が所得控除額を超えた場合には確定申告が必要となります。逆に、所得控除額を超えない場合は申告の義務はありません。
太陽光発電で「確定申告」の
会社員と個人事業主では基準が異なるため、自分の立場に応じて判断する必要があります。特に売電収入が安定的に発生する場合は、税務処理の方法や必要経費の計上について事前に確認しておくと安心です。
太陽光発電で「固定資産税」が課税される人・されない人
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や建物などの固定資産を所有している人に課される地方税です。太陽光発電システムについても、モジュールやパワーコンディショナーなどの設備全体が「償却資産」として扱われる場合があり、システムの規模によっては固定資産税の課税対象となります。
家庭用と産業用で異なる課税基準
課税の有無は「システム容量」で決まります。一般家庭で多く導入される「10kW未満」の太陽光発電設備は、固定資産税の対象外です。一方、「10kW以上」の産業用規模の設備では、固定資産税が課税されます。
固定資産税の計算方法
固定資産税額は次の計算式で求められます。
固定資産税額=固定資産の評価額 × 税率(1.4%)
例えば、500万円の太陽光発電設備を導入した場合は、
500万円 × 1.4% = 7万円
1,000万円規模の設備なら、
1,000万円 × 1.4% = 14万円
このように、設備規模が大きくなるほど税額も増加します。
固定資産税の注意点
実際の課税額は、設備の評価額や自治体ごとの判断によって異なる場合があります。特に産業用の大規模システムでは、評価額の算定方法や減価償却との関係も加わり、税額計算は複雑になることがあります。そのため、導入前に自治体や専門業者に確認しておくと安心です。