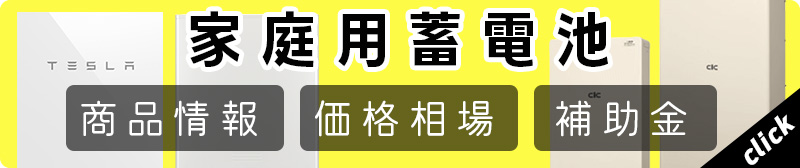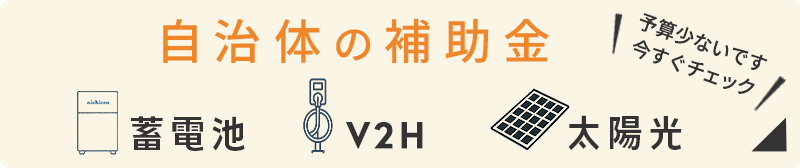エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
蓄電池の補助金とは
日本は台風や地震などの自然災害が多く、局所的あるいは広範囲にわたる停電が頻繁に発生します。停電は生活の不便にとどまらず、場合によっては命に関わる深刻な問題となることもあります。
政府による蓄電池導入の推進
こうした背景から、日本政府は環境保全の観点に加え、安全対策の一環として一般家庭や企業への蓄電池導入を推進しています。非常時に電力を確保できる蓄電池は、防災対策としても大きな役割を果たします。
蓄電池導入の課題と補助金制度
しかし、蓄電池の導入には設備費や工事費など多額の初期投資が必要となるため、普及の妨げになってきました。そこで考案されたのが、導入にかかる経済的負担を軽減する補助金制度です。この制度を利用すれば、一般家庭でも蓄電池を導入しやすくなり、非常時の備えを整えることが可能となります。
国と自治体、2種類の補助金
蓄電池に関する補助金は「国が行っているもの」と「自治体が行っているもの」の2種類があります。申請先や手続き方法はそれぞれ異なるため、事前にしっかり確認することが重要です。また、補助金の受付期間は統一されていませんが、タイミングが合えば国と自治体の補助金を併用することもでき、大幅な負担軽減につながります。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
蓄電池の国の補助金
国が実施する補助金は、蓄電池や太陽光システムの導入を検討している多くの世帯が対象となるため、毎年応募が集中し競争率が非常に高い傾向にあります。そのため、早めの情報収集と迅速な申請が欠かせません。
対象となる蓄電池と容量の影響
補助金の対象となる蓄電池は、種類や条件が限定されています。申請の際には、補助金の要件に合致する製品を選ぶことが重要です。また、給付額は施工費用に加えて蓄電池の容量によっても変動します。中途半端な容量を選ぶよりも、家庭の電力需要をしっかり満たす容量の製品を導入する方が補助金を有効に活用できます。さらに、算定の基準となるのは「蓄電容量」ではなく「初期実効容量」である点に注意が必要です。
補助金を受けるための条件
国の補助金を受けるには、いくつかの基準を満たす必要があります。代表的な条件としては、SII(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)に事前登録された災害対応型の機器であること、10kW未満の太陽光発電と併設可能な商品であること、新規に設置したものであること、中古品やレンタルは対象外であることなどが挙げられます。また、設置費用があらかじめ設定された目標価格以下であることも条件に含まれています。
蓄電池の国の補助金の概要
国が実施する蓄電池に関する補助金制度は、国庫を財源として運用されています。補助金の名称や制度内容はおおむね1年前後のサイクルで更新されるため、最新情報を常に確認することが欠かせません。
過去の補助金制度の例
2021年度には「分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けた実証事業(C事業)」という名称で、家庭用蓄電池の設置に関する補助金が実施されました。この制度は通称「DER補助金」と呼ばれ、広く知られるようになりました。予算規模は45.2億円で、住宅用だけでなく、業務用や産業用の蓄電システムを新規に設置する場合も対象となっていました。
申請窓口と管理団体
国の補助金は、一般社団法人「環境共創イニシアチブ(SII)」が申請の窓口を担っています。制度の詳細や申請条件、必要書類などもSIIを通じて案内されるため、補助金を活用する際には公式の情報を確認することが非常に重要です。
蓄電池の国の補助金額
補助金制度を利用すれば蓄電池導入の負担を大幅に減らせますが、実際にどの程度の金額が補助されるのか気になる人も多いでしょう。国から支給される補助額は、蓄電池の容量や契約条件によって異なります。
2021年度DER補助金の計算方法
2021年度のDER補助金では、「初期実効容量×4万円/kWh」という計算式で補助額が算出されました。ただし、実際に受け取れる金額は工事にかかった費用の3分の1が上限とされており、全額を補助してもらえるわけではありません。
補助の対象となる機器
DER補助金の対象は「太陽光発電システム」「蓄電池」「HEMS」の3つを揃えて設置する世帯でした。HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)は家庭で使用する電力を把握・最適化するためのシステムで、これに対しても補助金が適用されました。補助上限は10万円で、工事費用の2分の1以内という条件付きです。
補助金利用のポイント
補助金はあくまでも経済的負担を軽減するための制度であり、工事費用の満額を補填するものではありません。そのため、導入を検討する際には補助金でどの程度負担が減るのかを試算し、自身の家計計画に組み込むことが大切です。
蓄電池の国の補助金の申請の流れ
蓄電池の補助金制度には複数の組織が関わるため、申請にはいくつかのステップがあります。例えば、2021年度のDER補助金は6月から申請受付が始まりました。まずは補助金の対象条件を確認し、申請を行った後、交付決定が出るまでしばらく待機することになります。スムーズに進んだ場合でも、申請から交付決定までは数週間程度を要します。
契約締結のタイミングに注意
補助金の手続きにおいて注意すべき点は、蓄電池の設置業者との契約のタイミングです。見積もりや相談を行うことは可能ですが、正式な工事契約を結べるのは「補助金の交付が決定してから」に限られます。交付決定前に契約を進めてしまうと、補助金の対象外となってしまうため十分な注意が必要です。
工事から運転開始まで
交付が決定した後に設置工事が行われ、完了後は電力会社の認定を受けて運転が始まります。工事期間は住宅環境や設置機種によって異なりますが、一般的には数日から1週間程度で終了します。
実証事業への参加要件
2021年度のDER補助金では、年間を通じて約1週間程度の実証事業に参加すること、さらにその結果をまとめた報告書を提出することも必須条件とされていました。単なる設置支援にとどまらず、今後のエネルギー利用に役立つデータ収集という目的も含まれていたのです。
蓄電池の国の補助金がもらえるタイミング
蓄電池の設置に関する補助金は、交付決定が下りたからといって即座に受け取れるわけではありません。まず、申請内容が補助対象の設備基準を満たしているかどうかを、受け付け先である環境共創イニシアチブ(SII)が確認し、その上で随時交付が決定されていきます。
DER補助金の具体例
2021年度のDER補助金では、公募期間が2021年4月9日から12月24日までと設定されていました。交付決定の予定日は申請からおおよそ1~2週間後とされ、補助金の支払い期限は2022年3月31日までに定められていました。
交付決定のタイミングに注意
国の補助金は比較的スピーディーに審査・交付決定が進む点が特徴ですが、それでも必ず予定通り進むとは限りません。受け付け状況や審査の進み具合によって、交付決定日が前後する可能性があるため、補助金を前提にしたスケジュールには余裕を持つことが大切です。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
国が実施している補助金の申請方法
国が実施している補助金制度は、設置場所に関係なく全国で利用できるのが大きな特徴です。環境省や経済産業省が中心となって行っており、災害時の停電に備えて必要な電力を確保できる性能を持った太陽光発電システムや蓄電池などの導入を目的としています。
補助金額と申請の複雑さ
交付される補助金の額は、設置する設備の種類や性能、さらに工事費用によって異なります。ただし、申請方法はやや複雑で、予約申請・交付申請・実績報告といった複数の手続きを段階的に行う必要があります。そのため、あらかじめ全体の流れを把握して準備しておくことが、スムーズに補助金を受け取るためのポイントです。
蓄電池の補助金の予約申請
予約申請は、蓄電池や太陽光発電システムの導入を検討している段階で、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に対して行う最初の手続きです。この時点で、設置予定の発電所や蓄電システムの容量、太陽光発電との接続機器などが審査され、正式に申請手続きへ進めるかどうかが判断されます。
契約前に必ず行う手続き
予約申請は契約・購入・設置を行う前に済ませる必要があり、さらに定められた期限内に完了しなければなりません。この手続きを怠ると補助金の対象外となってしまうため、スケジュール管理が非常に重要です。
相見積もりの取得と補助金額の基準
申請には、原則として3社以上の施工業者から相見積もりを取ることが求められます。どの業者を最終的に選ぶかは自由ですが、補助金額は最安値の見積もりを基準に算定される仕組みです。ただし、設備を取り扱う業者が限られている場合や特注仕様、住宅一体型といった特殊な事情がある場合は、理由書を提出することで免除される可能性があります。
有効期限と次のステップ
予約申請が認可されると「予約決定通知書」が発行されます。ただし有効期限は決定日から90日間に限られており、この期間内に交付申請へ進む必要があります。もし電力会社との協議などで期限内に進めない場合は、「交付申請遅延届出書」を提出することで対応できます。
蓄電池の補助金の交付申請
交付申請は、予約決定日から90日以内、あるいはその年度に定められた交付申請提出期限までに行う必要があります。予約決定通知書を受け取った後は、電力会社と電力負担金や工事費について協議を進め、契約を結んだ上でSIIに対して交付申請を提出する流れとなります。そのため、余裕を持って協議に着手することが重要です。
申請期限の延長と注意点
もし90日以内に契約に至る見込みが立たない場合は、「交付申請遅延届出書」を提出することで期限を延長できます。ただし、交付申請の年度内提出期限は変更されないため、年度末に申請を行う場合はスケジュールを十分に確認しておく必要があります。
審査と交付決定通知書の発行
交付申請を終えると、SIIによって予約申請時の内容通りに契約が進められているかが審査されます。審査を通過すれば補助金交付の対象と認められ、「交付決定通知書」が発行されます。
補助金対象外にならないために
交付決定通知書が発行された後に初めて蓄電池の発注が可能となります。交付決定前に発注してしまうと補助金交付の対象外となってしまうため、契約・発注の順序には十分注意しなければなりません。
蓄電池の補助金の実績報告
実績報告は、蓄電池の発注から電気工事、設備の設置、引き渡し、そして支払いに至るまでの内容をまとめて提出する手続きです。この報告が完了しなければ補助金の交付は受けられないため、期限内に必ず行う必要があります。
補助事業期間と進行条件
実績報告が行われるまでの期間を「補助事業期間」と呼びます。この期間内に必ずしも発電システムから蓄電池へ電力が供給されている必要はありませんが、少なくとも蓄電池が稼働できる状態にしておくことが求められます。
支払い証明と必要書類
実績報告では費用の精算まで済ませておく必要があり、その証明として領収書の提出が義務付けられています。請求書では代用できないため注意が必要です。
認可と補助金の交付
実績報告も期限が設けられており、計画通りに全ての作業が完了したと認められると認可が下ります。その後、補助金額の決定通知書が発行され、補助金が正式に給付されます。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
国の補助金を申請する際のポイント

国の補助金は競争率が高く、例年早期に受付が終了します。
そのため、確実に補助金が受けられるようにミスなしで申請を済ませることを心がけるのはもちろん、できるだけ短期間で手続きを終えるのが良いでしょう。
国の補助金申請をする際に注意すべき点を、以下に紹介します。
予算には限度があり先着順で受付が終了する
国の事業だからといって、期限ぎりぎりに申請しても問題ないと考えるのは危険です。補助金には年度ごとに予算が設定されており、先着順で受付を行っているため、交付額が上限に達した時点で期限を待たずに受付が終了します。
早期終了の実例
蓄電池は太陽光発電と並んで需要が高く、毎年多くの申請が集中します。そのため、締め切り前に早期受付終了となるのが一般的です。実際に、翌年2月を期限としていたにもかかわらず、その年の8月から9月には受付が終了したケースも確認されています。
早めの準備が不可欠
蓄電池の購入や設置を検討し始めた段階で、補助金の予算残高を確認し、できるだけ早めに申請準備を進めることが重要です。予算の残り状況はSII(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)の公式ホームページで随時更新されているため、こまめにチェックしておきましょう。
蓄電池は交付が決定してから購入する
蓄電池の補助金は、申請さえすれば自動的に給付されるものではありません。審査を経て、条件を満たした場合にのみ交付が認められます。そのため、交付決定が下りる前に契約や発注を行ってしまうと、その経費は補助金の対象外となってしまいます。
契約や設置のタイミングに注意
補助金を確実に受け取るためには、契約や設置のタイミングを正しく管理することが大切です。特に、電力会社や施工業者と十分に協議した上で、交付が決定してから蓄電池を正式に購入するようにしましょう。
仮契約の活用
手続きをスムーズに進めるために、交付決定を前提とした仮契約を業者と結ぶことは問題ありません。あらかじめ準備を進めておけば、交付が下りた後に迅速に工事や設置に着手できます。特に、補助金の申請手続きを何度も経験している業者であれば、流れに沿って効率的にサポートしてくれるので安心です。
補助金の申請は個人では行えない
国の補助金を交付申請する場合、蓄電池を購入する個人が直接手続きを行うことはできません。補助対象となる蓄電池や関連設備の導入・工事を行う業者が、事前にSII(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)に「申請者代行登録」を行い、その上で手続きを代行する仕組みになっています。
業者による申請代行の仕組み
対象蓄電池を扱う業者であれば申請手続きの流れを熟知しているため、複雑な申請も安心して任せることができます。代行手数料は別途かかる場合と、施工費用に含まれている場合があるため、事前に見積もりで確認しておくと安心です。
自分でも確認しておく大切さ
国の補助金申請は手順が複雑なため、多くの場合、申請代行者がスケジュールを立てて必要書類や行程を指示する形で進められます。しかし、すべてを任せきりにせず、自分自身でも手続き内容を把握しておくことで、確実に補助金を受け取れる可能性が高まります。
信頼できる業者選びが鍵
業者選びの際には、これまでに補助金申請の実績が豊富な会社を選ぶのが賢明です。経験のある業者であればトラブルを避けやすく、スムーズに手続きを進めてもらえるでしょう。
補助金を受け取るまでには時間がかかる
蓄電池を設置する際は、工事を先に済ませてから補助金を申請することはできません。そのため、申請から交付までに一定の時間を要します。SII(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)の審査状況にもよりますが、一般的には申請から交付決定までにおよそ3カ月程度かかるとされています。導入を検討したら、できるだけ早めに施工業者へ相談するのが賢明です。
導入にかかる期間
申請から工事完了までの期間は、早くても2カ月、長い場合には半年近くかかることもあります。一方で、実際の設置工事や配線作業そのものは半日から1日程度で完了するケースがほとんどです。時間がかかるのは手続きや審査であり、工事そのものではない点を理解しておく必要があります。
手続きの具体的なステップ
導入の流れは以下のようになります。
まず複数の業者から見積もりを取り寄せて予約申請を行います。予約決定が下りたら、電力会社と工事費や電力負担金について協議し、契約を締結します。その後、交付申請を行い、承認されれば蓄電池の取り寄せ、現地調査、設置工事へと進みます。最後に引き渡しと支払いを済ませ、実績報告を提出することでようやく補助金が給付されます。
時間的余裕を持つことの大切さ
補助金を利用した蓄電池設置は、申請から受給までのプロセスに時間がかかるのが特徴です。スムーズに進めるには、余裕を持ったスケジュールを立て、早めに準備を進めることが重要です。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
蓄電池の地方自治体の補助金
蓄電池の補助金は地方自治体が独自に設定しているため、対象となる条件は自治体によって大きく異なります。一般的に共通しているのは、その自治体の区域内に居住していることや、税金の滞納がないことなどです。
補助対象機器の条件
多くの自治体では、交付対象となる蓄電池があらかじめ指定されています。容量の基準や、太陽光発電システムと連携できるかどうかといった条件が盛り込まれていることも多いため、購入前に必ず確認しておく必要があります。国の補助金と同様に、対象期間内に新品を設置することが条件とされ、中古品やレンタルは対象外となるケースが一般的です。
申請の流れ
地方自治体の補助金を利用する際は、まず居住している自治体で補助金が実施されているかどうかを確認することから始めます。その上で、自分の導入計画に合致する補助金制度があれば、条件を詳しく調べてから蓄電池を選定するのが基本的な流れです。
蓄電池の補助金の対応機器
地方自治体が実施している蓄電池の補助金に申請する場合も、所定の条件をすべて満たしている必要があります。
条件の内容は各自治体が独自に設定しているため、国のそれと同じではないということには注意してください。
申請期間は1年前後のスパンで区切られている場合が多く、予算に達した時点で受け付け終了となる点については国の補助金と同様です。
なお、国の補助金制度は基本的に家庭用蓄電池を対象としたものですが、地方自治体では民間企業向けにも補助金を用意しているところもあります。
家庭用と間違えて申請すると、審査落ちの結果が返ってくるまでの時間をロスしてしまうので事前によく確認しておきましょう。
補助金の内容や条件は各自治体によって異なるので、詳細は住まいがある自治体の公式ホームページなどをチェックしてみてください。
自治体からの蓄電池の補助額
各自治体でも限られた予算の中で補助金制度を展開しているため、それぞれで補助してもらえる金額は異なります。
東京都が実施した2021年度の家庭用蓄電池に関する補助金では、補助率は機器費の2分の1としていました。
国が「機器費+工事費」を補助の対象としていたのに対して、東京都では機器費に絞っている点が特徴的です。
補助の上限は蓄電容量1kWhあたり7万円まで、一戸あたりで受け取れる上限金額は42万円でした。
制度全体で確保されていた予算は30億7440万円と、比較的大規模なものとなっています。
蓄電池の自治体からの補助金がもらえるタイミング
地方自治体からの補助金は、国の補助金と比べて受給までに時間がかかる傾向があります。自治体ごとに限られた人員で手続きを進めているため、審査や処理のスピードは地域によって大きく異なる点に注意が必要です。
東京都の補助金手続きの流れ
東京都の場合、まず書類審査が行われ、必要に応じて現地調査が実施されます。制度の要件を満たしているかを厳密に確認した上で、問題がなければ交付決定通知書が発行されます。
申請書を提出してから交付決定通知書が届くまでには、おおよそ1ヵ月半から2ヵ月程度かかります。その後、申請者は設置業者と契約を結び、運転開始後に取得したデータを実績報告書として提出する必要があります。
助成金確定から支払いまで
東京都の例では、実績報告書を確認した後、5~6ヵ月ほどで助成金確定通知書が送付されます。そして確定通知の発行から約3週間後に、指定口座へ助成金が振り込まれる流れとなっています。結果的に、申請から実際の受給までに少なくとも7ヵ月程度を要するのが一般的です。
補助金を工事の前にもらうことは可能?
蓄電池の設置にかかる初期費用は小さいものではないため、できるだけ早く補助金を受け取りたいという人も多いでしょう。
実際の工事よりも前の段階で受け取れれば、家計への一時的な負担を軽減できます。
しかし、蓄電池に関わる補助金はその手続きの仕組みや制度趣旨の関係で、設備の設置・運転が完了した後の報告書が提出されて初めて支払いが確定するものです。
国・地方自治体の種類を問わず、蓄電池の補助金は工事より前に受け取ることはできないので覚えておきましょう。
蓄電池の価格相場
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
地方自治体が実施している補助金の申請方法
地方自治体が実施する蓄電池の補助金制度は、交付条件や金額、必要書類、手続き方法などが自治体ごとに異なります。中には補助金制度自体を設けていない自治体もあるため、利用を検討する際には必ず居住地の自治体に確認することが必要です。
個人で申請する必要がある
国の補助金は施工業者が代行申請を行う仕組みですが、地方自治体の補助金は原則として施主本人が申請を行います。そのため、国の補助金に比べると申請の負担は大きくなります。多くの自治体では工事を始める前に申請を済ませなければならず、申請方法も郵送・窓口提出・オンライン申請など自治体によって異なります。国と同様に申請期限が定められているため、事前に把握しておくことが大切です。
必要書類と手続きの流れ
提出する書類は国の補助金申請とほぼ同じ内容であることが多いため、施工業者に依頼すれば揃えやすいでしょう。工事前に必要書類を整え、申請書を提出すると、1週間から1カ月程度で審査が行われ、補助金の交付決定通知書が発行されます。その後に設置工事を実施し、完了後に報告書を提出すると補助金が支払われる流れです。
先着順で予算がなくなり次第終了
自治体の補助金も国と同じく先着順で受付が行われます。予算枠に達すると期限前でも募集が終了するため、導入を検討している場合はできるだけ早く申請することが重要です。
地方自治体の補助金を申請する際のポイント
地方自治体の補助金は、国の場合と違って地域によってタイミングや条件等がそれぞれ異なります。
しかし、条件が合致すれば国の補助金よりも申請者の数が少ないため、気持ちにゆとりをもって申請することができます。
とは言え、開始時期や受付の期限も自治体によって異なるため、常に最新の情報を収集しておいた方が良いでしょう。
以下に、地方自治体の補助金を申請する際のポイントを紹介していきます。
国の補助金と併用することもできる!
一つの蓄電池設置工事に対し、国が管轄している複数の補助金を併用して受け取ることはできません。一方、地方自治体の補助金は時期や地域によって受けられないこともありますが、国の補助金と併用することが可能です。
もちろん、どちらかの補助金の受付が終了していても、一方がまだ申請可能であれば片方だけ交付申請をすることもできます。
双方から補助金を受け取ることができれば、従来の価格よりも大幅にお得な金額で蓄電池の設置ができますし、見積もりで条件の良い施工業者が見つけられれば、さらに満足度は高くなるでしょう。
国と地方自治体、両方に申請を出す場合には、それぞれの条件をよく確認して、どちらの条件も満たしている蓄電池を選ぶ必要があります。
また、申請や契約、施工のタイミングをよく確認してから作業を進めるようにしましょう。
補助金の申請は個人で行う
国の補助金は申請代行者しか行えませんが、地方自治体の場合は原則個人で交付申請を行います。
そのため、必要書類は自分で用意する必要がありますし、申請書の作成や必要書類の添付、スケジュール調整、自治体から交付される決定通知書の受け取りなどをすべて自分で管理しなければなりません。
手順が複雑で手続きが面倒、忙しくて申請ができないという場合には、費用はかかりますが申請代行を利用することも可能です。
元々国の補助金を申請する予定であればタイミングとしてはそれほど大きなずれが生じませんし、地域密着型の施工業者ならば、そのエリアの地方自治体の補助金交付申請についても詳しいため、安心して任せられます。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
確実に補助金を受け取るために気を付けたいこと

蓄電池の設置費用が高額であるように、それを補助するための制度で受け取れる金額も少ないものではありません。
そのため、万が一補助金を受け取ることができなかった場合の負担は看過できないと言えるでしょう。
予期せぬとトラブルを防ぎ、確実に補助金を受け取るためには以下の点について十分注意して手続きを行ってください。
信頼できる業者を選ぶ
蓄電池の補助金を確実に受け取るためには、まず信頼できる販売店や設置業者を選ぶことが欠かせません。蓄電池の仕様や機能は専門用語が多く、一般の消費者がすべてを正確に理解するのは簡単ではありません。さらに、補助金制度の条件や手続きにも専門用語が登場するため、知識がないまま進めてしまうと誤解や手続きミスにつながりかねません。
専門知識を持つ正規業者の強み
正規の販売・設置業者であれば、蓄電池や補助金制度に関する知識を持ち合わせているため、契約時に適切な説明やアドバイスを受けながら手続きを進められます。特に初めて蓄電池を導入する家庭にとっては、専門知識を持つ業者の存在が大きな安心材料となります。
悪質業者に注意
家庭用蓄電池の需要が高まる中で、参入業者の数も増えています。しかし、中には違法性が疑われる悪徳業者も存在するのが現実です。信頼できる業者を見極めるためには、販売・施工の実績やアフターサービスの充実度を確認することが重要です。
業者選びのポイント
業者を選ぶ際は、公式ホームページだけでなく、実際の利用者による口コミや体験談も参考にしましょう。また、インターネット上には複数の業者に一括で見積りを依頼できるサービスもあり、効率的に比較検討を行うことができます。こうした仕組みを上手に活用することで、安心して蓄電池を導入できる環境を整えることができます。
蓄電池の補助金を申請することを業者に伝えておく
補助金制度を利用するつもりである旨を販売店・設置業者に伝えておくことも、確実に補助金を受け取るために重要なポイントです。
市販されている蓄電池の多くは補助金の対象であるものの、すべての機種が対象となっている訳ではありません。
補助金の金額も容量によって変動するため、正確な見積りを算出するためには業者の協力を得るのが近道です。
事前に補助金に関する情報を共有しておけば、支給の条件に当てはまっているかどうかを確認しやすくなります。
補助金に関しての知識や実績が豊富な業者であれば、対象となる機種・具体的な申請方法などについてアドバイスをもらえる可能性も高いです。
特に地方自治体の補助金制度については地域密着型の業者が強い傾向にあるので、不安点や疑問は積極的に相談してみてください。
指定された期間内に設置する
蓄電池の補助金を受け取るためには、原則として「新規の設置」であることが条件です。すでに設置を完了してしまった後に申請しても、補助金は交付されません。必ず申請から設置までの流れを守る必要があります。
設置期限とスケジュール管理
補助金制度には申請期限だけでなく、設備の設置期限も定められています。たとえ申請期限内に手続きを進めていたとしても、設置期限を過ぎてしまえば補助金を受け取ることはできません。契約は交付決定の通知が届いてから行うため、設置期限から逆算して余裕を持って申請することが大切です。さらに、審査にかかる時間も考慮して計画を立てましょう。特に自治体が実施する補助金制度では審査に時間がかかる傾向があるため注意が必要です。
実績報告書の提出義務
補助金には、設備の設置・稼働を証明するための「実績報告書」の提出が求められる場合があります。すべての制度で必須というわけではありませんが、多くの補助金制度では交付の前提条件となっています。制度によっては設備の写真を提出することも求められるため、証拠資料の準備も忘れてはいけません。
期限管理の徹底
補助金に関する期限は「申請期限」「設置期限」「報告書や証拠資料の提出期限」と複数に分かれています。これらは必ずしも同じ日程ではなく、バラバラに設定されているケースが多いのが特徴です。補助金を確実に受け取るためには、それぞれの期限を正確に把握し、スケジュールを管理することが不可欠です。
早めに補助金を申請する
蓄電池の補助金制度は、申請から実際に受給するまでに一定の時間がかかります。国の補助金は比較的手続きが早いと言われていますが、それでもおよそ1ヶ月程度は見込んでおく必要があります。さらに、設置業者の工事スケジュールによっても期間は変動するため、少しでも早く受け取りたい場合は、申請をできるだけ早めに済ませることが大切です。
予算上限と先着順のリスク
近年は一般家庭での蓄電池導入が注目されるようになり、補助金制度の認知度も高まっています。その結果、利用を希望する人が増え、受付開始から間もなく予算上限に達してしまうケースも珍しくありません。多くの制度は抽選ではなく先着順であるため、確実に補助金を受け取りたいのであれば、スピーディーに意思決定して申し込むことが求められます。
継続的な情報収集の重要性
条件を満たしていても、申請が締め切られていれば補助金を受け取ることはできません。そのため、既に当年度の補助金が終了している場合には、次年度の制度に向けて情報をこまめにチェックし続けることが重要です。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
家庭用蓄電池の補助金の申請に延長はある?

補助金スケジュールが延長される可能性
家庭用蓄電池の補助金は、年度によって申請期間が延長される場合があります。実際に2020年度の「災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金」では、当初6月末で終了予定だった募集期間が、最終的に8月末まで延長されました。これは新型コロナウイルスの影響により、申請準備に時間を要する家庭が多かったことを考慮した措置です。
延長されても予算が上限に達すれば終了
ただし、補助金には必ず予算が設定されています。そのため、募集期間が延長されたとしても、予算が上限に達した時点で打ち切られる点には注意が必要です。
情報収集の重要性
予算の消化状況は、SII(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)の公式ホームページで随時告知されています。確実に補助金を受け取るためには、社会情勢や予算の進捗を確認しながら早めに申請準備を整えることが重要です。
エコ発電本舗の「商品」「補助金」メニュー
補助金を受けるときに注意したいポイント!

家庭用蓄電池の補助金制度を利用すると購入や設置にかかる費用の負担が軽減されるのは魅力的です。しかし、家庭用蓄電池を手に入れるときに必ず補助金を利用できるとは限りません。
ここでは補助金制度を活用する際に注意しておいた方が良いポイントをわかりやすく紹介します。
制度の利用を検討するときには一通り理解してから準備に取り掛かりましょう。
支給条件をよく確認する
家庭用蓄電池の補助金制度は国や地方自治体が目的を持って進めている事業なので、補助をしたことによって目的が達成されなければなりません。
補助金の支給条件はいくつも設定されていて、同じ名称の補助金事業でも年度によって条件が異なる部分もあります。
一つでも条件を満たしていないことがわかったら支給されないので、蓄電池の設置や申請の準備を始める段階で支給条件を詳しく確認しましょう。
家庭用蓄電池の機器の種類や設備費、購入時期や契約時期などに加え、太陽光発電システムが既に設置されている必要があるかどうかを確認が必要です。
蓄電池の設置を依頼する業者にはどの補助金制度を利用したいかを伝えて、見積もりの時点で補助金の条件を満たす仕様になっているかどうかを細かくチェックしましょう。
書類上で条件を満たしていることが確認できないと補助対象にはならないので気を付けなければならないポイントです。
申請期限に注意する
補助金制度の申請期間についても注意が必要です。
あらかじめスケジュールされている期限があり、延長されない限りは申請期限に間に合わなかったときには補助金を利用できません。
日にちだけでなく時刻まで定められているのが一般的なので、日時を正確に把握して申請が遅れないようにしましょう。また、予算上限に達したときのように申請期限よりも早く終了することもあります。
国も地方自治体も予算を組んで運用していますが、緊急で他に予算を使う必要が生じた際などには打ち切りになる可能性もないわけではありません。
家庭用蓄電池は早く設置して運用してもらいたいため、基本的に募集は抽選ではなく先着順です。申請期限ぎりぎりでも大丈夫だと思わずに、できるだけ早く準備を整えて申請しましょう。
特に全国から利用できる国の補助金や、人口や住宅数が多い東京都の補助金は早期終了しやすい傾向があります。
必要書類をすべてそろえる
補助金の申請では必要書類がすべて整っていなければなりません。
制度によって必要書類には違いがありますが、申請書や提案書、見積書などの用意が必要です。
国の補助金では団体概要や直近の決算報告書、補助事業の要件及びその審査に関する説明書などの提出が求められています。
書類の不足や記入漏れなどがあると補助金事業として採択されず、支給されないリスクがあるので気を付けましょう。
書類は蓄電池の設置について相談している業者に代行して依頼してもらうのが安心です。補助金制度を利用して蓄電池を設置したいことを伝えれば対応してくれるので必要書類の提出は業者に任せましょう。
ほかにも使える補助金制度がある!
家庭用蓄電池の導入に使用することが可能な補助金制度は以上で紹介したものだけではありません。
正式名称にも略称にも蓄電池という名前が入っていない補助金制度でも、補助金の支給条件と家庭用蓄電池の設置の仕方によっては活用できる可能性あります。
ここでは家庭用蓄電池に利用できると考えられる代表的な補助金制度を紹介するので、条件に合うように設置できるかどうかを検討してみましょう。
ZEH補助金
ZEH補助金はネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の推進を目的としている補助金で、一定の基準を満たすZEHに対して支給されるのが特徴です。
ZEHは生活によって使用される一次エネルギーの消費量を、再生可能エネルギーの発電システムの導入によってトータルでエネルギー収支をゼロにした住宅です。
建物の断熱性を高めたり、効率の高い設備システムを導入することで省エネルギーの実現と発電したエネルギーの有効活用を進めることでZEHを実現できます。
太陽光発電システムに蓄電池を付帯させて設置することも可能なので、ZEH補助金を活用することが可能です。
ただし、ZEH補助金の2021年度の公募は三次公募受付まで終了しています。今後も制度が継続される可能性が十分にあるので利用を検討してみましょう。
VPP補助金
VPP補助金は分散型エネルギーリソース(DER)を構築し、バーチャルパワープラント(VPP、仮想発電所)を整備する実証を目的として出されている補助金です。
DERの補助金とも言われていて、VPPを作り上げるための基盤となるDERとして家庭や工場の蓄電池などの設置に補助が出る仕組みになっています。エネルギーリソースを増やし、遠隔で統合制御できるようにするVPPの実証実験に参加することが前提となる補助金制度です。
VPP補助金はVPP基盤整備事業やVPPアグリゲーター事業などに分かれていて、蓄電池が対象になっているVPPリソース導入促進事業は2021円1月18日の時点で交付申請の受付が終わってしまっています。
実証実験の進捗によっては再度募集がある可能性もあるのでVPP補助金の動向も確認しておくと良いでしょう。